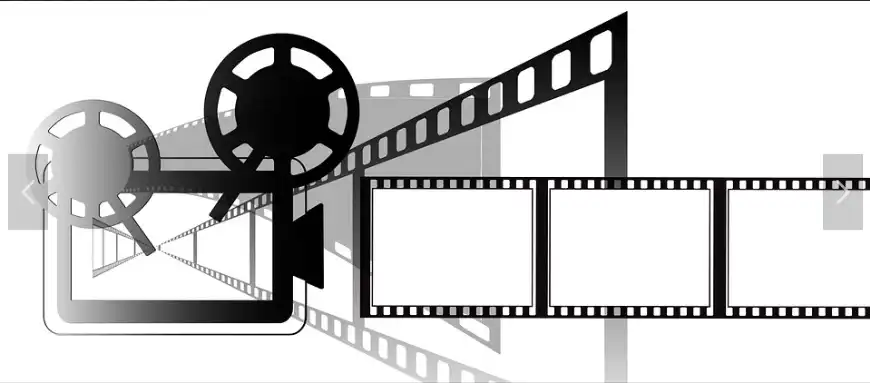えいがずきのつどい けいじばん
映画好きの集い掲示板
説明
Explanation映画好きの集いの掲示板です。
毎回新旧テーマ映画を挙げ、それについて会員の忌憚の無い感想を書き込みます。
掲示板
BBS管
管理者さん (9jkb4tgs)2025/5/22 06:52 (No.1445588)削除課題映画、第23回映画好きの集い(旧作)(2025年8月10日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
上
上終結城さん (8g07wmfj)2025/5/30 20:59削除旧作『パルプ・フィクション』(1994年)クエンティン・タランティーノ監督
1.この映画を選んだ理由
クエンティン・タランティーノ監督作品は以前から好きで、第一作『レザボア・ドッグス』(1992)から『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)までほとんど観てきました。そのなかでも映画手法の斬新さと面白さの点で、本作が群を抜いていると思います。
この映画は時間軸を意図的に交錯させていて、一度観ただけではよくわからないでしょう。おそらく二回観て初めて全体の構図が理解できるようになっています。本作でタランティーノはアカデミー脚本賞を受賞。
2.鑑賞テーマ
鑑賞のテーマを下記のようにしました。7月下旬になったら少し詳しいコメントを投稿する予定です。
(1)この映画は観る人によって好き嫌いがはっきり出ると思います。映画評論界の重鎮、双葉十三郎はこの作品をまったく評価していませんが、他の評論家、たとえば小林信彦、芝山幹郎、町山智浩などは本作を絶賛しています。では正直にいって、みなさんはこの映画が面白かったですか、それともつまらなかった(または、よくわからなかった)でしょうか? できればその理由も教えてください。
(2)この映画には濃いキャラクターの人物が多数でてきますが、印象に残った登場人物はいましたか?
(3)ストーリーと無関係な無駄話が延々続くのが、この映画の特徴のひとつです。面白かった話題はありましたか?
(4)この映画には「映画オタク」の監督らしい、過去の映画、TV番組などからの引用やオマージュが多数あるとのことです。(私にはほとんどわかりませんでしたが)みなさんはなにか気づいたシーンがありましたか?
1.この映画を選んだ理由
クエンティン・タランティーノ監督作品は以前から好きで、第一作『レザボア・ドッグス』(1992)から『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)までほとんど観てきました。そのなかでも映画手法の斬新さと面白さの点で、本作が群を抜いていると思います。
この映画は時間軸を意図的に交錯させていて、一度観ただけではよくわからないでしょう。おそらく二回観て初めて全体の構図が理解できるようになっています。本作でタランティーノはアカデミー脚本賞を受賞。
2.鑑賞テーマ
鑑賞のテーマを下記のようにしました。7月下旬になったら少し詳しいコメントを投稿する予定です。
(1)この映画は観る人によって好き嫌いがはっきり出ると思います。映画評論界の重鎮、双葉十三郎はこの作品をまったく評価していませんが、他の評論家、たとえば小林信彦、芝山幹郎、町山智浩などは本作を絶賛しています。では正直にいって、みなさんはこの映画が面白かったですか、それともつまらなかった(または、よくわからなかった)でしょうか? できればその理由も教えてください。
(2)この映画には濃いキャラクターの人物が多数でてきますが、印象に残った登場人物はいましたか?
(3)ストーリーと無関係な無駄話が延々続くのが、この映画の特徴のひとつです。面白かった話題はありましたか?
(4)この映画には「映画オタク」の監督らしい、過去の映画、TV番組などからの引用やオマージュが多数あるとのことです。(私にはほとんどわかりませんでしたが)みなさんはなにか気づいたシーンがありましたか?
藤
藤堂勝汰さん (9jxpimbp)2025/5/31 15:56削除第23回映画好きの集い(旧作)
パルプ・フィクション
鑑賞テーマについて
(1)この映画は観る人によって好き嫌いがはっきり出ると思います。映画評論界の重鎮、双葉十三郎はこの作品をまったく評価していませんが、他の評論家、たとえば小林信彦、芝山幹郎、町山智浩などは本作を絶賛しています。
では正直にいって、みなさんはこの映画が面白かったですか、それともつまらなかった(または、よくわからなかった)でしょうか? できればその理由も教えてください。
(answer)
僕も上終さん程ではありませんがクエンティン・タランティーノ監督作品は好きです。
狂気と純粋さが混在し、人間の矛盾が描かれている作品が多いと自分は感じています。
このパルプ・フィクションも冒頭のカップルがレストランで金儲けを画策しているシーンで始まり、最後そのカップルがレストランで強盗を起こし、結局いとも簡単に失敗し、出ていくシーンで終わるというなかなか憎い演出をしてくれています。
面白いのは、このシーンが最後ではなく、ボクサーのブッチ(ブルース・ウィリス)がギャングのボスのマーセルスを助け、命拾いをして町を出ていくシーンが本当の最後だというところです。
こういったからくり仕立てもタランティーノの力があってこそ成せる業だと思います。
(2)この映画には濃いキャラクターの人物が多数でてきますが、印象に残った登場人物はいましたか?
(answer)
やはり、ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)の掛け合いが一番印象に残りました。
ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)はマーセルス(ヴィング・レイムス)から彼の愛妻ミア(ユマ・サーマン)の世話を頼まれ、彼女との間に秘密を作るシーンですね。
ジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)は神の存在を感じ、足を洗うことを決意した時に、カップルの強盗に直面し、殺さずに自分の金を渡すシーンですね。
秘密を作るという意味では、ブッチ(ブルース・ウィリス)もかなり強烈な印象を持たせる存在です。
最後、マーセルスを助け、無罪放免になる所では、ブッチとマーセルが秘密を作って去っていくという夫婦の秘密という締め方で終わらせているあたり、心憎い演出である。
(3)ストーリーと無関係な無駄話が延々続くのが、この映画の特徴のひとつです。面白かった話題はありましたか?
(answer)
色々あったと思いますが、ミアのマッサージをした男がマッサージだけで高いところから突き落とされたというヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)のやり取りである。
たかがそれぐらいで突き落とされるはずがないとか、他に何かあったはずだというやり取りが一番印象的でした。
(4)この映画には「映画オタク」の監督らしい、過去の映画、TV番組などからの引用やオマージュが多数あるとのことです。(私にはほとんどわかりませんでしたが)みなさんはなにか気づいたシーンがありましたか?
(answer)
正直ここが何かのオマージュだとは気が付かなかったが、タランティーノ自身がジュールスの友人、ジミー役で出演していて笑ってしまった。ジュールスにやっかい事を持ち込まれるわけだが、意外に声が高く、セリフも棒読みとまではいかないが、ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)の掛け合いの中にタランティーノのセリフがあるので、二人がいつ吹き出してしまうのか観ているこっちが心配になった(笑)
【最後に】
最近の映画は型にはまり、起承転結を短時間でまとめようとしているお行儀のよい作品ばかりの中、このタランティーノ監督のような鬼才が求められているのかもしれない。
恐らくかつて映画好きの集いに属していた佐藤ルイ子(石野夏実)さんはこのような作品が好きなのでは? と感じた次第である。
先般同じく属していた浅丘さんのところに一緒に行った際に、「note」というアプリで精力的に発信し続けていると昔と変わらない言葉数とスピードでまくしたてられ、凄いと圧倒させられました。興味のある方は彼女の活動をチェックしてみて欲しいと思います。
■石野夏実の記事一覧|note(ノート)
https://note.com/ishinon_natsumin/all
パルプ・フィクション
鑑賞テーマについて
(1)この映画は観る人によって好き嫌いがはっきり出ると思います。映画評論界の重鎮、双葉十三郎はこの作品をまったく評価していませんが、他の評論家、たとえば小林信彦、芝山幹郎、町山智浩などは本作を絶賛しています。
では正直にいって、みなさんはこの映画が面白かったですか、それともつまらなかった(または、よくわからなかった)でしょうか? できればその理由も教えてください。
(answer)
僕も上終さん程ではありませんがクエンティン・タランティーノ監督作品は好きです。
狂気と純粋さが混在し、人間の矛盾が描かれている作品が多いと自分は感じています。
このパルプ・フィクションも冒頭のカップルがレストランで金儲けを画策しているシーンで始まり、最後そのカップルがレストランで強盗を起こし、結局いとも簡単に失敗し、出ていくシーンで終わるというなかなか憎い演出をしてくれています。
面白いのは、このシーンが最後ではなく、ボクサーのブッチ(ブルース・ウィリス)がギャングのボスのマーセルスを助け、命拾いをして町を出ていくシーンが本当の最後だというところです。
こういったからくり仕立てもタランティーノの力があってこそ成せる業だと思います。
(2)この映画には濃いキャラクターの人物が多数でてきますが、印象に残った登場人物はいましたか?
(answer)
やはり、ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)の掛け合いが一番印象に残りました。
ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)はマーセルス(ヴィング・レイムス)から彼の愛妻ミア(ユマ・サーマン)の世話を頼まれ、彼女との間に秘密を作るシーンですね。
ジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)は神の存在を感じ、足を洗うことを決意した時に、カップルの強盗に直面し、殺さずに自分の金を渡すシーンですね。
秘密を作るという意味では、ブッチ(ブルース・ウィリス)もかなり強烈な印象を持たせる存在です。
最後、マーセルスを助け、無罪放免になる所では、ブッチとマーセルが秘密を作って去っていくという夫婦の秘密という締め方で終わらせているあたり、心憎い演出である。
(3)ストーリーと無関係な無駄話が延々続くのが、この映画の特徴のひとつです。面白かった話題はありましたか?
(answer)
色々あったと思いますが、ミアのマッサージをした男がマッサージだけで高いところから突き落とされたというヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)のやり取りである。
たかがそれぐらいで突き落とされるはずがないとか、他に何かあったはずだというやり取りが一番印象的でした。
(4)この映画には「映画オタク」の監督らしい、過去の映画、TV番組などからの引用やオマージュが多数あるとのことです。(私にはほとんどわかりませんでしたが)みなさんはなにか気づいたシーンがありましたか?
(answer)
正直ここが何かのオマージュだとは気が付かなかったが、タランティーノ自身がジュールスの友人、ジミー役で出演していて笑ってしまった。ジュールスにやっかい事を持ち込まれるわけだが、意外に声が高く、セリフも棒読みとまではいかないが、ヴィンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)の掛け合いの中にタランティーノのセリフがあるので、二人がいつ吹き出してしまうのか観ているこっちが心配になった(笑)
【最後に】
最近の映画は型にはまり、起承転結を短時間でまとめようとしているお行儀のよい作品ばかりの中、このタランティーノ監督のような鬼才が求められているのかもしれない。
恐らくかつて映画好きの集いに属していた佐藤ルイ子(石野夏実)さんはこのような作品が好きなのでは? と感じた次第である。
先般同じく属していた浅丘さんのところに一緒に行った際に、「note」というアプリで精力的に発信し続けていると昔と変わらない言葉数とスピードでまくしたてられ、凄いと圧倒させられました。興味のある方は彼女の活動をチェックしてみて欲しいと思います。
■石野夏実の記事一覧|note(ノート)
https://note.com/ishinon_natsumin/all
無
無敗の藤原さん (95c8u6fd)2025/6/15 16:44削除人がバンバン死ぬわ、薬物を使うわ、言葉の言い回しも、見るもの全てが新しいものだらけでした。
【設問1】
ズバリこの映画が面白かったか、つまらなかったか。
→
ディープな映画ファンが発してるレベルでは心酔してないですけど、ユニークさに溢れた、確かに面白い映画だと思います。
特にキャラがいいと思います。どのキャラも良い人じゃないけど、ぶっとんだ個性と共感できるポイントがある。
【設問2】
印象に残った登場人物は。
→
みんなクセがありすぎて好きになれるキャラクターは居なかったですけど、ウルフって呼ばれてた裏世界のプロフェッショナルって感じがしてよかったです。
あと、ジュールスの悪人だけど哲学に悩むところもよかったです。ヴィンセントが死んだとき、ジュールスが一緒にいなかったからやっぱり足を洗ったのかな。
【設問3】
無駄話の中で面白かった話題は。
→
無駄話多いんですけど、いかにもな状況を伝えるためのセリフとか、物語を運ぶためのセリフとかをダサいと思ってる監督なのかもしれませんね。
私も説明セリフを嫌うタイプですけど、それの究極系だなと。
リアリティとか没入感が生まれると思ってます。
好きだった会話は、ミアとヴィンセントの別れ際に、テレビ番組のジョークを今更話すところ。今!?って感じなんですけどそれが逆に粋だなと。
【設問4】
オマージュに気づいたシーンがあったか。
→
マリリン・モンローのスカートが捲れるところは見たことある気がします。
他に知ってるオマージュ見つからなかったけど、ブッチが刀で人を斬るシーンは違和感ありすぎるので何かのオマージュなんだと勘ぐります。
【設問1】
ズバリこの映画が面白かったか、つまらなかったか。
→
ディープな映画ファンが発してるレベルでは心酔してないですけど、ユニークさに溢れた、確かに面白い映画だと思います。
特にキャラがいいと思います。どのキャラも良い人じゃないけど、ぶっとんだ個性と共感できるポイントがある。
【設問2】
印象に残った登場人物は。
→
みんなクセがありすぎて好きになれるキャラクターは居なかったですけど、ウルフって呼ばれてた裏世界のプロフェッショナルって感じがしてよかったです。
あと、ジュールスの悪人だけど哲学に悩むところもよかったです。ヴィンセントが死んだとき、ジュールスが一緒にいなかったからやっぱり足を洗ったのかな。
【設問3】
無駄話の中で面白かった話題は。
→
無駄話多いんですけど、いかにもな状況を伝えるためのセリフとか、物語を運ぶためのセリフとかをダサいと思ってる監督なのかもしれませんね。
私も説明セリフを嫌うタイプですけど、それの究極系だなと。
リアリティとか没入感が生まれると思ってます。
好きだった会話は、ミアとヴィンセントの別れ際に、テレビ番組のジョークを今更話すところ。今!?って感じなんですけどそれが逆に粋だなと。
【設問4】
オマージュに気づいたシーンがあったか。
→
マリリン・モンローのスカートが捲れるところは見たことある気がします。
他に知ってるオマージュ見つからなかったけど、ブッチが刀で人を斬るシーンは違和感ありすぎるので何かのオマージュなんだと勘ぐります。
返信
返信3
管
管理者さん (9jkb4tgs)2025/5/22 06:53 (No.1445589)削除課題映画、第23回映画好きの集い(新作)(2025年8月10日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2025/6/8 10:28削除この映画を選んだ理由
初めは文句なく楽しめた『侍タイムスリッパー』にしようと思ったのだが、せっかくならもっと考えさせるような映画にしようと思い直した。
早川監督の『PLAN75』はカンヌで新人監督を対象とした賞も受賞もしているし、今年のカンヌにも『ルノワール』という作品を出品している。『PLAN75は』私もまだ観ていなかったのだが、超高齢化や安楽死というテーマ性もあり、どんな映画なのかという期待をもってこの作品に決めた。
課題① 映画内における75歳以上の安楽死を容認する「プラン75」という制度に対して、あなたのご意見をお聞かせください。
課題② どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残りましたか。
課題➂ ラストシーンも含め、説明を省き観ている人にゆだねる表現が多かったですが、この手法についてどう思いますか。
課題④ この映画の自由感想をどうぞ。
初めは文句なく楽しめた『侍タイムスリッパー』にしようと思ったのだが、せっかくならもっと考えさせるような映画にしようと思い直した。
早川監督の『PLAN75』はカンヌで新人監督を対象とした賞も受賞もしているし、今年のカンヌにも『ルノワール』という作品を出品している。『PLAN75は』私もまだ観ていなかったのだが、超高齢化や安楽死というテーマ性もあり、どんな映画なのかという期待をもってこの作品に決めた。
課題① 映画内における75歳以上の安楽死を容認する「プラン75」という制度に対して、あなたのご意見をお聞かせください。
課題② どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残りましたか。
課題➂ ラストシーンも含め、説明を省き観ている人にゆだねる表現が多かったですが、この手法についてどう思いますか。
課題④ この映画の自由感想をどうぞ。
藤
藤堂勝汰さん (9kaibcjg)2025/6/9 14:55削除『PLAN75』を鑑賞して
課題① 映画内における75歳以上の安楽死を容認する「プラン75」という制度に対して、あなたのご意見をお聞かせください。
(answer)
生き続ける権利、死を選ぶ権利が許容されるPLAN75であるが、貧困や生活苦から選択肢はあってないようなものであると思った。
本人がそれでも生き続けたいと思うか、そんな思いから解放されたいと思うかでPLAN75という器の形が変わるなと思った。
それとは別に安楽死の問題は、生き続けることが本人に苦痛を強い続ける場合にやむを得ず発動されるものだと思うので、こちらは容認したいと考える、
政府が推し進めるPLAN75に対しては反対の立場である。
課題② どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残りましたか。
(answer)
倍賞千恵子を久々にスクリーンで見た。
歳をとった感は否めないが、声の張りや仕草は若々しいと思った。
シーンで言うと、プラン75の職員である青年・岡部ヒロム(磯村勇斗)が掲示板に張り紙をしている時に何かを投げつけられるわけだが、だれが何の為に投げつけたのかが今一つ背景が無く、理解できなかった。
課題➂ ラストシーンも含め、説明を省き観ている人にゆだねる表現が多かったですが、この手法についてどう思いますか。
(answer)
この監督の特徴なのだろうが、背景や説明を極力省いている為、課題②も含めて理解できない部分が多々あった。
課題④ この映画の自由感想をどうぞ。
(answer)
正直言うと、観ている途中、観終わった後もやり切れなく、後味のいい映画ではなかった。
ついつい監督の意図は? と言う事を考えてしまい、やっぱり人間は情に支えられ、死ぬ最期まで、その情から逃れる事はできないという事だったのかなとも思ったが、そんなに単純なものでも無さげな展開であった。
誰かの為に、食い扶持を減らすために山に登るというのは楢山節考 ( 深沢七郎,)からヒントを得たストーリーであるのだろう。
映画「楢山節考」の方が時代は違えど、食い扶持を減らすために自ら死を選ぶという犠牲愛が描かれていると思い、腑に落ちると感じた。
課題① 映画内における75歳以上の安楽死を容認する「プラン75」という制度に対して、あなたのご意見をお聞かせください。
(answer)
生き続ける権利、死を選ぶ権利が許容されるPLAN75であるが、貧困や生活苦から選択肢はあってないようなものであると思った。
本人がそれでも生き続けたいと思うか、そんな思いから解放されたいと思うかでPLAN75という器の形が変わるなと思った。
それとは別に安楽死の問題は、生き続けることが本人に苦痛を強い続ける場合にやむを得ず発動されるものだと思うので、こちらは容認したいと考える、
政府が推し進めるPLAN75に対しては反対の立場である。
課題② どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残りましたか。
(answer)
倍賞千恵子を久々にスクリーンで見た。
歳をとった感は否めないが、声の張りや仕草は若々しいと思った。
シーンで言うと、プラン75の職員である青年・岡部ヒロム(磯村勇斗)が掲示板に張り紙をしている時に何かを投げつけられるわけだが、だれが何の為に投げつけたのかが今一つ背景が無く、理解できなかった。
課題➂ ラストシーンも含め、説明を省き観ている人にゆだねる表現が多かったですが、この手法についてどう思いますか。
(answer)
この監督の特徴なのだろうが、背景や説明を極力省いている為、課題②も含めて理解できない部分が多々あった。
課題④ この映画の自由感想をどうぞ。
(answer)
正直言うと、観ている途中、観終わった後もやり切れなく、後味のいい映画ではなかった。
ついつい監督の意図は? と言う事を考えてしまい、やっぱり人間は情に支えられ、死ぬ最期まで、その情から逃れる事はできないという事だったのかなとも思ったが、そんなに単純なものでも無さげな展開であった。
誰かの為に、食い扶持を減らすために山に登るというのは楢山節考 ( 深沢七郎,)からヒントを得たストーリーであるのだろう。
映画「楢山節考」の方が時代は違えど、食い扶持を減らすために自ら死を選ぶという犠牲愛が描かれていると思い、腑に落ちると感じた。
無
無敗の藤原さん (95c8u6fd)2025/6/15 16:42削除【課題1】
「プラン75」という制度に対しての意見。
→
制度があること事態は悪くないと思います。ただ作中で書かれているように、斡旋するような雰囲気は良くないなと感じますね。
私なんかは年金がもらえないと思われる世代なので70歳までは働けるように今から筋トレするぞ!ってやってますけど、70歳から更に先はどこまで生きれるかわからないですから、プラン75があったらお世話になるかもしれないと思います。
けど、人生長く生きて、最後の結論が不幸に基づくものなの嫌なんですよね〜。最後は幸せだったって気持ちで人生の結論出したいです。
【課題2】
どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残ったたか。
→
ミチさんと、先生と呼ばれてる若い女の人との最後の電話。たぶん全員がここで胸を痛めたと思います。「いつも話を聞いてくれありがとうございました」って電話越しに頭を下げるシーン本当に悲しくて…。これは名作だなと思いました。
それと、ミチさんが安楽死のベッドで隣の叔父さんを見たときの表情。なぜミチさんが死ぬのをやめたのか、ハッキリとはわからないけれど、叔父さんの死ぬところを見てるあの表情で悲しみと恐怖を感じました。演技で説得力をもたせるのすごいと思いました。
あと、叔父さんが献血手帳を付けてて、それももう捨てちゃうって話した時。あれもなんかじわ〜って来るんですよね。人生が終わるってことは無になるってことなんだと思い知らされます。
【課題3】
説明を省き観ている人にゆだねる表現についてどう思うか。
→
ラスト10分ぐらいで色んなことが起きましたけど、そこがあまり理解できなかったんですよね。
叔父は病気だったのか?マリアさんが叔父の遺体を運び出す手伝いをした経緯は?死んだあとでも叔父を運び出したかった理由は?ここがわからなかったけど、ラストを長引かせるのは得策じゃないのでこれでよかったのかも。
逆に説明がなくて痺れたシーンがあって、叔父をヒロムが迎えに来たシーンで「いつも4時に目が覚めるのに今日に限って――」ってセリフがこれ以上ない完璧な言葉だと思いました。
【課題4】
自由感想。
→
すごい映画ですよね。リアルな設定を組んでて、まずそこがすごい。プラン75の発端ともなった殺人事件と、その後介護施設のセキュリティが強くなったりとか。プラン75の宣伝を流してるテレビの電源を切っちゃう人とか、ハローワークで検索しても求人0件になっちゃうとことか。
この話にはリアリティが不可欠だってわかってる監督さんなんでしょうね。
ちょっと人には勧めにくい映画ではありますけど、映画ごころと熱量を感じるすごい名作だと思いました。
「プラン75」という制度に対しての意見。
→
制度があること事態は悪くないと思います。ただ作中で書かれているように、斡旋するような雰囲気は良くないなと感じますね。
私なんかは年金がもらえないと思われる世代なので70歳までは働けるように今から筋トレするぞ!ってやってますけど、70歳から更に先はどこまで生きれるかわからないですから、プラン75があったらお世話になるかもしれないと思います。
けど、人生長く生きて、最後の結論が不幸に基づくものなの嫌なんですよね〜。最後は幸せだったって気持ちで人生の結論出したいです。
【課題2】
どのシーン、またどの俳優の演技が印象に残ったたか。
→
ミチさんと、先生と呼ばれてる若い女の人との最後の電話。たぶん全員がここで胸を痛めたと思います。「いつも話を聞いてくれありがとうございました」って電話越しに頭を下げるシーン本当に悲しくて…。これは名作だなと思いました。
それと、ミチさんが安楽死のベッドで隣の叔父さんを見たときの表情。なぜミチさんが死ぬのをやめたのか、ハッキリとはわからないけれど、叔父さんの死ぬところを見てるあの表情で悲しみと恐怖を感じました。演技で説得力をもたせるのすごいと思いました。
あと、叔父さんが献血手帳を付けてて、それももう捨てちゃうって話した時。あれもなんかじわ〜って来るんですよね。人生が終わるってことは無になるってことなんだと思い知らされます。
【課題3】
説明を省き観ている人にゆだねる表現についてどう思うか。
→
ラスト10分ぐらいで色んなことが起きましたけど、そこがあまり理解できなかったんですよね。
叔父は病気だったのか?マリアさんが叔父の遺体を運び出す手伝いをした経緯は?死んだあとでも叔父を運び出したかった理由は?ここがわからなかったけど、ラストを長引かせるのは得策じゃないのでこれでよかったのかも。
逆に説明がなくて痺れたシーンがあって、叔父をヒロムが迎えに来たシーンで「いつも4時に目が覚めるのに今日に限って――」ってセリフがこれ以上ない完璧な言葉だと思いました。
【課題4】
自由感想。
→
すごい映画ですよね。リアルな設定を組んでて、まずそこがすごい。プラン75の発端ともなった殺人事件と、その後介護施設のセキュリティが強くなったりとか。プラン75の宣伝を流してるテレビの電源を切っちゃう人とか、ハローワークで検索しても求人0件になっちゃうとことか。
この話にはリアリティが不可欠だってわかってる監督さんなんでしょうね。
ちょっと人には勧めにくい映画ではありますけど、映画ごころと熱量を感じるすごい名作だと思いました。
返信
返信3
管
管理者さん (9jkb4tgs)2025/5/22 06:56 (No.1445591)削除第23回文横映画好きの集い(自由映画)(2025年8月10日)について、ご自由に感想をお書込みください!
返信
返信0
管
管理者さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:45 (No.1395860)削除課題映画、第22回映画好きの集い(旧作)(2025年5月11日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
無
無敗の藤原さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:46削除「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」
というタイトルを見てポカンとしてる人のほうが多いと思います。
ちょうど私世代の人が子どものときに見る映画なのですが、今なお語られることも名作と評されていていますし、私自身の好きな映画ベスト5には入れたい作品となってます。
それでも子ども向けのアニメーション作品が皆さんの興味をそそらないのは何となく想像できるのでもう一押し紹介しておきますと、
映画秘宝という雑誌の2001年のベスト映画で1位を取ってます。(洋画も含めた選定で)
新しい体験を味わうつもりで是非見ていただきたいです。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
というタイトルを見てポカンとしてる人のほうが多いと思います。
ちょうど私世代の人が子どものときに見る映画なのですが、今なお語られることも名作と評されていていますし、私自身の好きな映画ベスト5には入れたい作品となってます。
それでも子ども向けのアニメーション作品が皆さんの興味をそそらないのは何となく想像できるのでもう一押し紹介しておきますと、
映画秘宝という雑誌の2001年のベスト映画で1位を取ってます。(洋画も含めた選定で)
新しい体験を味わうつもりで是非見ていただきたいです。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:46削除【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
(回答)
『起』が問題提起だとするならば、20世紀博での過去の物、ヒーロー、事象紹介が必要であると感じた。その為かなりの時間を割かざるを得なかったのだと思います。
特に当時の子供たちには20世紀?ってどんな時代かを面白おかしく説明してあげないとイマイチぴんと来ないと思われるためである。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
(回答)
しんちゃんの以下のセリフで伝えているのだと思います。
「オラ、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロともっと一緒に居たいから… 喧嘩したり、頭にきたりしても一緒が良いから… あと、オラ大人になりたいから… 大人になって、おねいさんみたいなきれいなおねいさんといっぱいお付き合いしたいから!」
頭にくることやいろいろ立ちふさがる問題は増えてくることが予想されるが、それでも大人になることから逃げる事はしたくない。
大人になったら、大人の知恵で乗り切ればなんとかなると思いたかったからだと思います。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
(回答)
以下の感想でも記しましたが、現代の人間関係や自然環境、社会的ストレスへのアンチテーゼが盛り込まれている作品である為でしょう。
21世紀が始まったばかりである2001年にこの映画を作ることの意義、それは20世紀への回顧と決別である。
21世紀はもはや古き良き時代をも回顧することが許されない激動のストレス社会になるという予言の元、今だったら一旦立ち止まり、まだ選べるという可能性を示したかったのではないでしょうか?
また考えてもらいたいというメッセージが盛り込まれているからでしょう。
(その他感想)
恐らくクレヨンしんちゃんシリーズの映画を観たのは、2回目だと思います。1回目がどんな作品だったか覚えていませんが、TVでふと点けてそのまま流すように見ていた記憶があります。
映画の課題テーマとならなかったら、観ない映画だと思います。
そういった意味では、そういう機会を無敗さんに頂けた事に感謝いたします。
設問2にも関係しますが、この映画のテーマはアニメ全般に多い「勧善懲悪」からは一線を画しており、正直言うと観終わって後味すっきりと言うわけにはいきませんでした。
と言うのも、ケンとチャコの考え方、行動は根本的に「悪」に根差したものではなく、現代の人間関係や自然環境、社会的ストレスへの痛烈な批判がそうさせている、というアンチテーゼが盛り込まれている為である。
21世紀も4半世紀が経過し、今年は大阪万博が55年ぶりに開催される年でもあり、改めて残りの75年の進むべき方向性を考えさせてくれる映画ではないでしょうか?
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
(回答)
『起』が問題提起だとするならば、20世紀博での過去の物、ヒーロー、事象紹介が必要であると感じた。その為かなりの時間を割かざるを得なかったのだと思います。
特に当時の子供たちには20世紀?ってどんな時代かを面白おかしく説明してあげないとイマイチぴんと来ないと思われるためである。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
(回答)
しんちゃんの以下のセリフで伝えているのだと思います。
「オラ、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロともっと一緒に居たいから… 喧嘩したり、頭にきたりしても一緒が良いから… あと、オラ大人になりたいから… 大人になって、おねいさんみたいなきれいなおねいさんといっぱいお付き合いしたいから!」
頭にくることやいろいろ立ちふさがる問題は増えてくることが予想されるが、それでも大人になることから逃げる事はしたくない。
大人になったら、大人の知恵で乗り切ればなんとかなると思いたかったからだと思います。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
(回答)
以下の感想でも記しましたが、現代の人間関係や自然環境、社会的ストレスへのアンチテーゼが盛り込まれている作品である為でしょう。
21世紀が始まったばかりである2001年にこの映画を作ることの意義、それは20世紀への回顧と決別である。
21世紀はもはや古き良き時代をも回顧することが許されない激動のストレス社会になるという予言の元、今だったら一旦立ち止まり、まだ選べるという可能性を示したかったのではないでしょうか?
また考えてもらいたいというメッセージが盛り込まれているからでしょう。
(その他感想)
恐らくクレヨンしんちゃんシリーズの映画を観たのは、2回目だと思います。1回目がどんな作品だったか覚えていませんが、TVでふと点けてそのまま流すように見ていた記憶があります。
映画の課題テーマとならなかったら、観ない映画だと思います。
そういった意味では、そういう機会を無敗さんに頂けた事に感謝いたします。
設問2にも関係しますが、この映画のテーマはアニメ全般に多い「勧善懲悪」からは一線を画しており、正直言うと観終わって後味すっきりと言うわけにはいきませんでした。
と言うのも、ケンとチャコの考え方、行動は根本的に「悪」に根差したものではなく、現代の人間関係や自然環境、社会的ストレスへの痛烈な批判がそうさせている、というアンチテーゼが盛り込まれている為である。
21世紀も4半世紀が経過し、今年は大阪万博が55年ぶりに開催される年でもあり、改めて残りの75年の進むべき方向性を考えさせてくれる映画ではないでしょうか?
清
清水伸子さん (921a7cxd)2025/3/6 17:41削除「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!大人帝国の逆襲」を観て
今日本文化を代表するものの一つが漫画やアニメーションになってきているのではないでしょうか。なのでこの映画の会の課題映画に取り上げられたのもなるほどと思いました。
課題1 起の部分の時間配分は良かったか?
特に違和感はありませんでした。自然に物語の世界に入っていけました
課題2.今を生きる根拠はこの映画で伝えきれているか?
遠藤さんと同じく「オラ、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロともっと一緒に居たいから… 喧嘩したり、頭にきたりしても一緒が良いから… あと、オラ大人になりたいから… 大人になって、おねいさんみたいなきれいなおねいさんといっぱいお付き合いしたいから!」というセリフと、飛び降りようとするケンとチャコを鳩が羽ばたいて止める場面などから「今を生きていこうよ」というメッセージが伝わってきました
課題3.なぜ名作と言われているのか
20世紀博という発想がとても面白く、そこに広がるノスタルジックな風景に引き込まれる心情をリアルに感じさせながら、それと対比させるように、不完全であっても自分の家族を愛しく大切に思う子どもの姿を描いて今を生きていくんだという強いメッセージを伝えている点ではないかと思いました
今日本文化を代表するものの一つが漫画やアニメーションになってきているのではないでしょうか。なのでこの映画の会の課題映画に取り上げられたのもなるほどと思いました。
課題1 起の部分の時間配分は良かったか?
特に違和感はありませんでした。自然に物語の世界に入っていけました
課題2.今を生きる根拠はこの映画で伝えきれているか?
遠藤さんと同じく「オラ、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロともっと一緒に居たいから… 喧嘩したり、頭にきたりしても一緒が良いから… あと、オラ大人になりたいから… 大人になって、おねいさんみたいなきれいなおねいさんといっぱいお付き合いしたいから!」というセリフと、飛び降りようとするケンとチャコを鳩が羽ばたいて止める場面などから「今を生きていこうよ」というメッセージが伝わってきました
課題3.なぜ名作と言われているのか
20世紀博という発想がとても面白く、そこに広がるノスタルジックな風景に引き込まれる心情をリアルに感じさせながら、それと対比させるように、不完全であっても自分の家族を愛しく大切に思う子どもの姿を描いて今を生きていくんだという強いメッセージを伝えている点ではないかと思いました
上
上終結城さん (8g07wmfj)2025/3/27 16:10削除1.はじめに
小生が観た数少ないアニメ映画のひとつが、同じ原恵一監督の『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』(2002)で、これも無敗さんから薦められた映画だった。じつをいうと『戦国大合戦』は、なかなかよかったのである。すこし感動したといってもいいくらいだ。おバカでお下劣なこども向けアニメの印象がある『クレヨンしんちゃん』シリーズ。そこへシリアスなストーリーやテーマを入れ込む手法に、意表を突かれた。
そんなわけで本作(『戦国大合戦』の前作にあたる)も、ふざけたタイトルとは無関係に、すこし期待して観た。結果は、大人の鑑賞にも十分堪える映画だと思った。
2.課題について
【設問1】映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか? 悪かったでしょうか?
【回答1】
プログラムピクチャーに定番の、いわゆるアバンストーリー(『男はつらいよ』シリーズなら最初に出る寅さんの夢のようなもの)かと思ったが、そのわりに長かった。このくだりが終わり、本筋が動き出すのは映画開始後約15分(全体の1/6が経過)。しかしここで、大人たち(ひろし、みさえが代表)が自分の子供時代のヒーローやヒロインに夢中になる姿がつよく印象づけられ、それが本筋への導入になっている。
【設問2】この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
【回答2】
社会の約束事(たとえば家族を養うための労働や育児義務、家事など)から解放されれば、大人たちは子供時代に戻って、好きなだけ遊びたいのが本音。その幻想から、大人たちを我に返らせたものは「家族との幸福な思い出や家族の絆(きずな)」だった(スイッチはひろしの足の臭いだが)。家族でこの映画を観にきている観客を考えれば、これは妥当な展開といえる。
しかしライフスタイルや幸福の尺度が多様化し、家族に対する価値観が相対的に低下している現在、家族神話は説得力を失いつつあるのかもしれない。
【設問3】なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
【回答3】
しんちゃん映画の観客動員(興行的成功)は、まず子供がその映画を面白がるかがポイントだろう。しかし「名作」かどうかを評価するのは大人。この映画は親世代(2001年時点で40歳前後。しんのすけの父親ひろしの世代)のノスタルジーを存分に刺激するコンテンツになっていて、大人受けがよかったのだろう。
原恵一監督(1959年生まれ)もひろしと同世代。本作では監督自身の子供時代の雰囲気を随所に盛り込んでいる。たとえば挿入歌は、大阪万博(1970)前後に流行った曲。「ケンとメリー~愛と風のように」(1972)、「白い色は恋人の色」(1969)、「今日までそして明日から」(1971)など。
本作が高く評価された理由は、以下の要素がうまく融合したためだと思う。映画のマーケティング的には文字通り、親子で楽しめる内容になっている。
(1)スラップスティック(ドタバタ喜劇)とお下劣なギャグ(おなら、足の臭いなど) ⇒ 子供受け
(2)1970年代への郷愁 ⇒ 大人受け
(3)シリアスなテーマ。本心では仕事や育児を放棄したい大人の願望。「大人帝国」 ⇒ 評論家受け
(4)矛盾を抱えた敵役(ケンとチャコ)の造形 ⇒ 評論家受け
(5)既存の名作からの借用『スピード』、『未知との遭遇』など ⇒ 映画愛好家受け
3.その他の感想
たしかに大人にとって仕事は、家族を養うための義務の一面がある(それだけではないが)。しかし40数年間働いて退職してみると、毎日自分のやりたいことだけをやっていい身分になっている(もちろん、ある程度の収入と健康は必要)。これは小生の世代(昭和30年代生れ)だから可能なのかもしれない(年金制度を含め)。今の現役世代の人たちにはどんな未来が待っているのか?
小生が観た数少ないアニメ映画のひとつが、同じ原恵一監督の『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』(2002)で、これも無敗さんから薦められた映画だった。じつをいうと『戦国大合戦』は、なかなかよかったのである。すこし感動したといってもいいくらいだ。おバカでお下劣なこども向けアニメの印象がある『クレヨンしんちゃん』シリーズ。そこへシリアスなストーリーやテーマを入れ込む手法に、意表を突かれた。
そんなわけで本作(『戦国大合戦』の前作にあたる)も、ふざけたタイトルとは無関係に、すこし期待して観た。結果は、大人の鑑賞にも十分堪える映画だと思った。
2.課題について
【設問1】映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか? 悪かったでしょうか?
【回答1】
プログラムピクチャーに定番の、いわゆるアバンストーリー(『男はつらいよ』シリーズなら最初に出る寅さんの夢のようなもの)かと思ったが、そのわりに長かった。このくだりが終わり、本筋が動き出すのは映画開始後約15分(全体の1/6が経過)。しかしここで、大人たち(ひろし、みさえが代表)が自分の子供時代のヒーローやヒロインに夢中になる姿がつよく印象づけられ、それが本筋への導入になっている。
【設問2】この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
【回答2】
社会の約束事(たとえば家族を養うための労働や育児義務、家事など)から解放されれば、大人たちは子供時代に戻って、好きなだけ遊びたいのが本音。その幻想から、大人たちを我に返らせたものは「家族との幸福な思い出や家族の絆(きずな)」だった(スイッチはひろしの足の臭いだが)。家族でこの映画を観にきている観客を考えれば、これは妥当な展開といえる。
しかしライフスタイルや幸福の尺度が多様化し、家族に対する価値観が相対的に低下している現在、家族神話は説得力を失いつつあるのかもしれない。
【設問3】なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
【回答3】
しんちゃん映画の観客動員(興行的成功)は、まず子供がその映画を面白がるかがポイントだろう。しかし「名作」かどうかを評価するのは大人。この映画は親世代(2001年時点で40歳前後。しんのすけの父親ひろしの世代)のノスタルジーを存分に刺激するコンテンツになっていて、大人受けがよかったのだろう。
原恵一監督(1959年生まれ)もひろしと同世代。本作では監督自身の子供時代の雰囲気を随所に盛り込んでいる。たとえば挿入歌は、大阪万博(1970)前後に流行った曲。「ケンとメリー~愛と風のように」(1972)、「白い色は恋人の色」(1969)、「今日までそして明日から」(1971)など。
本作が高く評価された理由は、以下の要素がうまく融合したためだと思う。映画のマーケティング的には文字通り、親子で楽しめる内容になっている。
(1)スラップスティック(ドタバタ喜劇)とお下劣なギャグ(おなら、足の臭いなど) ⇒ 子供受け
(2)1970年代への郷愁 ⇒ 大人受け
(3)シリアスなテーマ。本心では仕事や育児を放棄したい大人の願望。「大人帝国」 ⇒ 評論家受け
(4)矛盾を抱えた敵役(ケンとチャコ)の造形 ⇒ 評論家受け
(5)既存の名作からの借用『スピード』、『未知との遭遇』など ⇒ 映画愛好家受け
3.その他の感想
たしかに大人にとって仕事は、家族を養うための義務の一面がある(それだけではないが)。しかし40数年間働いて退職してみると、毎日自分のやりたいことだけをやっていい身分になっている(もちろん、ある程度の収入と健康は必要)。これは小生の世代(昭和30年代生れ)だから可能なのかもしれない(年金制度を含め)。今の現役世代の人たちにはどんな未来が待っているのか?
池
池内健さん (9inzq9ox)2025/4/29 16:04削除懐かしいにおいで昔を思い出させるという設定は、プルースト「失われた時を求めて」に出てくるマドレーヌと茶のエピソードにつながる。においが持つ喚起力の強さは誰もが経験していることだと思うが、そのにおいを全国に拡散して洗脳しようというイエスタデイワンスモアの姿にはオウム真理教を連想した。こういう「飛び道具」を使わなければ広げられない思想はまがい物だろう。この計画は、いつか大人になりたいしんちゃんの活躍で阻止される。その中でも、ひろしやみさえを我に返らせるため靴のにおいを利用するのはしんちゃんの本領発揮。おしっこがしたいときの「尿意」のような言葉をおならで何というか、というやりとりもとぼけていて笑えた。
【設問1】起承転結の『起』の時間配分
1970年の大阪万博の場面から始まり、タイムスリップ物なのか、あるいは設定自体を現代から昔に移したのかと、最初はとまどった。大人向けテーマパークであることがわかるまでにかなり時間を割いているのは、当時を知らない人にも魅力を納得させないと、大人たちがどうして昔に戻りたい気持ちになるか伝わらないからだろう。特に長いとは感じなかったので、良かったのではないか。
【設問2】今を生きる方を選ぶ
懐かしい過去は隔離され管理された場所でしか再現できなかった。個々人が過去の思い出やレトログッズを大事にするのはけっこうだが、社会全体として過去に生きることは極端な管理社会でしか成立しないということを伝えていると思った。
【設問3】なぜ名作か
年を取り、世間の動きについていけなくなると、つい「昔は良かった」と言いたくなる。しかし、それでは子どもたちの未来を奪うことになってしまうということを説教くさくなく伝えているからではないか。
【設問1】起承転結の『起』の時間配分
1970年の大阪万博の場面から始まり、タイムスリップ物なのか、あるいは設定自体を現代から昔に移したのかと、最初はとまどった。大人向けテーマパークであることがわかるまでにかなり時間を割いているのは、当時を知らない人にも魅力を納得させないと、大人たちがどうして昔に戻りたい気持ちになるか伝わらないからだろう。特に長いとは感じなかったので、良かったのではないか。
【設問2】今を生きる方を選ぶ
懐かしい過去は隔離され管理された場所でしか再現できなかった。個々人が過去の思い出やレトログッズを大事にするのはけっこうだが、社会全体として過去に生きることは極端な管理社会でしか成立しないということを伝えていると思った。
【設問3】なぜ名作か
年を取り、世間の動きについていけなくなると、つい「昔は良かった」と言いたくなる。しかし、それでは子どもたちの未来を奪うことになってしまうということを説教くさくなく伝えているからではないか。
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2025/5/2 17:08削除「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲」を観て
先日の大阪旅行で、70年に開催された跡地の大阪万博公園に行ったばかりなので、ナイスタイミングだった。(リアルタイムでは行っていないが)
この映画では太陽の塔を含めた当時の万博の様子や、昭和の夕焼けの街の様子がとても綺麗でリアルだと感じた。アニメ制作のクレジットの中に、京都アニメーションとあったので、その辺は京アニが担当したのかもしれないと思った。
ちなみに、この映画は2001年4月の制作だが、2009年には原作者の臼井さんが登山中の事故死。そして2019年には例の京アニ事件があって、スタジオは全焼し多くのスタッフがケガを負ったり亡くなったりした。もしかしたら、この映画に携わったスタッフも犠牲になったのかもしれない。
映画とは直接関係のないことで恐縮だが、そんなことを漠然と考えたりもした。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
それは特に気にならず、ちょうどよいと思った。クライマックスに持っていくための伏線の時間だろう。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
それは十分、伝えきれていると思う。昨日までのごく普通の生活のありがたさがわかり、家族とともに今を生きることの意義に気づいたのだと思う。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
子供向けの割には生きることに対する奥深さがある。もちろん、子供が飽きないようにギャグを交えたりして、表現には工夫がされているが。
また一方で、20世紀博ということで、大人が見れば高度成長期の風景は懐かしい。劇中に挿入されたバズの「ケンとメリー」や拓郎の「今日までそして明日から」などの歌も含めて、大人にも受けたのがヒットの要因だろう。
多分、無敗さんのようにこの映画を子供の頃に観て、大人になってから再度観たら、また新たな感動が生まれるのだろうなあ、と思った。(その辺を無敗さんに聞いてみたい。私にもそういう映画があるので)
先日の大阪旅行で、70年に開催された跡地の大阪万博公園に行ったばかりなので、ナイスタイミングだった。(リアルタイムでは行っていないが)
この映画では太陽の塔を含めた当時の万博の様子や、昭和の夕焼けの街の様子がとても綺麗でリアルだと感じた。アニメ制作のクレジットの中に、京都アニメーションとあったので、その辺は京アニが担当したのかもしれないと思った。
ちなみに、この映画は2001年4月の制作だが、2009年には原作者の臼井さんが登山中の事故死。そして2019年には例の京アニ事件があって、スタジオは全焼し多くのスタッフがケガを負ったり亡くなったりした。もしかしたら、この映画に携わったスタッフも犠牲になったのかもしれない。
映画とは直接関係のないことで恐縮だが、そんなことを漠然と考えたりもした。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
それは特に気にならず、ちょうどよいと思った。クライマックスに持っていくための伏線の時間だろう。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
それは十分、伝えきれていると思う。昨日までのごく普通の生活のありがたさがわかり、家族とともに今を生きることの意義に気づいたのだと思う。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
子供向けの割には生きることに対する奥深さがある。もちろん、子供が飽きないようにギャグを交えたりして、表現には工夫がされているが。
また一方で、20世紀博ということで、大人が見れば高度成長期の風景は懐かしい。劇中に挿入されたバズの「ケンとメリー」や拓郎の「今日までそして明日から」などの歌も含めて、大人にも受けたのがヒットの要因だろう。
多分、無敗さんのようにこの映画を子供の頃に観て、大人になってから再度観たら、また新たな感動が生まれるのだろうなあ、と思った。(その辺を無敗さんに聞いてみたい。私にもそういう映画があるので)
藤
藤野燦太郎さん (9fhs4rfz)2025/5/6 17:22削除クレヨンしんちゃん 大人帝国の逆襲 感想 藤野燦太郎
ジブリ以外にアニメを見たことがないので、不安でした。
1. 映画の時間配分の問題。「起」にかなりの時間を使っている。これでよかったのか。
この作品が2001年4月公開なのにほんの5か月前の世界を、別世界(20世紀)として区切って扱っている。1991年にバブル崩壊が起こってそれから日本人は経験のない異常事態にさらされた。2001年にはもう元には戻れないというあきらめが広がり、高度成長期を懐かしむ風潮が広がり始めた。20世紀は労働が報われ、給料は上がるのが当たり前、土地も必ず上がり、会社における地位も安泰、精神的にも安定した時代だったが、21世紀の現在は、今挙げたものがすべて怪しくなり、メンタルクリニックや精神科が大繁盛しています。バブルを知っている中高年は過去を懐かしむのは当たり前ですが、2001年はちょっと頑張れば元の世界に戻れると思う人が一定数いたように思います。
前提を明白にしないと成立しない映画なので、「起」に時間を割いたのでしょう。
2. 過去に生きるか、今を生きるか? 今を生きるを選ぶ根拠が伝えきれているか。
しんちゃんの言葉に「おら、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロと一緒にいたいから」で子供にはしっかり伝わっていると思います。この映画は大人の鑑賞にも耐えるように作られたようですが、大人には少し伝わりにくいと思いました。
3. なぜ名作と言われているのか
このような高度成長期(昭和)を懐かしむ映画を2001年に作るのは冒険だったと思われます。
しかもアニメで先鞭を切ったのは評価され、そういう意味で名作なのだと思います。
これで手ごたえをつかんで2005年に大ヒット作「三丁目の夕日」ができたのかな??
ジブリ以外にアニメを見たことがないので、不安でした。
1. 映画の時間配分の問題。「起」にかなりの時間を使っている。これでよかったのか。
この作品が2001年4月公開なのにほんの5か月前の世界を、別世界(20世紀)として区切って扱っている。1991年にバブル崩壊が起こってそれから日本人は経験のない異常事態にさらされた。2001年にはもう元には戻れないというあきらめが広がり、高度成長期を懐かしむ風潮が広がり始めた。20世紀は労働が報われ、給料は上がるのが当たり前、土地も必ず上がり、会社における地位も安泰、精神的にも安定した時代だったが、21世紀の現在は、今挙げたものがすべて怪しくなり、メンタルクリニックや精神科が大繁盛しています。バブルを知っている中高年は過去を懐かしむのは当たり前ですが、2001年はちょっと頑張れば元の世界に戻れると思う人が一定数いたように思います。
前提を明白にしないと成立しない映画なので、「起」に時間を割いたのでしょう。
2. 過去に生きるか、今を生きるか? 今を生きるを選ぶ根拠が伝えきれているか。
しんちゃんの言葉に「おら、父ちゃんや母ちゃんやひまわりやシロと一緒にいたいから」で子供にはしっかり伝わっていると思います。この映画は大人の鑑賞にも耐えるように作られたようですが、大人には少し伝わりにくいと思いました。
3. なぜ名作と言われているのか
このような高度成長期(昭和)を懐かしむ映画を2001年に作るのは冒険だったと思われます。
しかもアニメで先鞭を切ったのは評価され、そういう意味で名作なのだと思います。
これで手ごたえをつかんで2005年に大ヒット作「三丁目の夕日」ができたのかな??
無
無敗の藤原さん (95c8u6fd)2025/5/9 20:26削除まずはみなさん、私が大好きな映画を見てくださってありがとうございます。
みなさんと集まる当日は時間の都合で多くは語らないと思いますが、掲示板には語りたいだけ長々と語りたいと思います。
まずは本映画が2Dアニメーションであることから。
3DCG(CGはコンピュータグラフィック)アニメーションならおそらくディズニー、つまりアメリカが最先端を進んでおりますが、2Dアニメーションであれば日本が技術的にも予算的にも最大だと思います。
少し前にフランスの2DCGアニメーションを見ましたが、日本のアニメみたいにカメラを自在に動かすことは無いですし、表情のバリュエーションも日本は凄いと思ってます。
更に本映画はコンピューターグラフィックをほとんど使用してないので、厚紙に描いた背景にキャラクターの絵を重ねて一コマ一コマカメラで撮影する技法を使っています。キャラクターの着色もコンピューターを使わず、配合済みの絵の具のような塗料(アニメカラーと言います)で塗っています。
その結果、絵画の世界が動いてるような不思議な映像が出来上がるのです。皆さんの中でも夕焼けがきれいだなとか、街並みがきれいだなって感想を持った人もおられると思います。
そして、アニメーションという制作技法の特性上意図していないものが映像に映らない、ということが魅力のひとつだとも思います。
どういうことかと言うと、実写の映画ならカメラを回した時に遠くの方で自転車を漕いでる人がたまたま映っているってことがあり得ます。ですが、アニメなら遠くに自転車を漕ぐ人を描かなければいけないので、偶然というのは99%ありません。どんな些細なことでも監督や演出さんや原画さんが決定してそこに映していると思っていいです。
だから描いてある情報以上の濃密さが生まれたり、魅入ったりするんだと思います。
あと本作の魅力として音楽があるでしょうね。
挿入歌は恐らく昭和の曲でしょうけど、私が聞いても懐かしさに浸れるような気持ちになります。そしてひろしの回想で流れるアコースティックギターの曲と、しんのすけがタワーを登る時に流れるオーケストラの曲(曲名:21世紀を取り戻せ)が感情を増幅させました。
この映画は辻褄を追っていくと納得できるような内容ではないのですが、音楽と演技によって感情の流れが出来上がってると思うんですよね。
だから何度見てもしんのすけがタワー登るシーンで泣いてしまうわけです(笑)。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
→
一応ハリウッドの三幕構成で30/30/30分になってるからバランスがいいって解説してる人もいました。
けれど、私は最初見た時に20世紀博のシーン長いなーって思った記憶があります。
ただし、短い映画で満足感得られるのでそこは成功だなと思います。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
→
過去の思い出の方が強く描写されているので、実は今を生きるってことについては描写が不足しているかなと感じます。
でもそれを補ってしまうほど音楽と演技が素晴らしかったと思います。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
→
なんか、不思議な映画ですよね(笑)。
コメディかと思ったらホラー、と思ったらラブロマンス、家族のヒューマンドラマ。
コメディは必ずしも笑えるわけではないし、最初は少し引いた目線でこの映画を見ると思うんです。
でも、しんのすけの両親がトラックの荷台に乗っているのを見て声を掛けるも無視される、しんのすけがひまわりを背負って家の縁石の上を走って手を振るあのシーンを観る頃に、魅入ってしまったなと気付きました。
粗のある作りではあるんですけど、この映画が名作と呼ばれる所以は、魂が感じられるからだと思います。
いい作品にしたいって現場の空気感がいい作画を引き出し、いい背景美術を引き出し、いい演技を引き出し、いい音楽を引き出すんじゃないかと思います。
みなさんと集まる当日は時間の都合で多くは語らないと思いますが、掲示板には語りたいだけ長々と語りたいと思います。
まずは本映画が2Dアニメーションであることから。
3DCG(CGはコンピュータグラフィック)アニメーションならおそらくディズニー、つまりアメリカが最先端を進んでおりますが、2Dアニメーションであれば日本が技術的にも予算的にも最大だと思います。
少し前にフランスの2DCGアニメーションを見ましたが、日本のアニメみたいにカメラを自在に動かすことは無いですし、表情のバリュエーションも日本は凄いと思ってます。
更に本映画はコンピューターグラフィックをほとんど使用してないので、厚紙に描いた背景にキャラクターの絵を重ねて一コマ一コマカメラで撮影する技法を使っています。キャラクターの着色もコンピューターを使わず、配合済みの絵の具のような塗料(アニメカラーと言います)で塗っています。
その結果、絵画の世界が動いてるような不思議な映像が出来上がるのです。皆さんの中でも夕焼けがきれいだなとか、街並みがきれいだなって感想を持った人もおられると思います。
そして、アニメーションという制作技法の特性上意図していないものが映像に映らない、ということが魅力のひとつだとも思います。
どういうことかと言うと、実写の映画ならカメラを回した時に遠くの方で自転車を漕いでる人がたまたま映っているってことがあり得ます。ですが、アニメなら遠くに自転車を漕ぐ人を描かなければいけないので、偶然というのは99%ありません。どんな些細なことでも監督や演出さんや原画さんが決定してそこに映していると思っていいです。
だから描いてある情報以上の濃密さが生まれたり、魅入ったりするんだと思います。
あと本作の魅力として音楽があるでしょうね。
挿入歌は恐らく昭和の曲でしょうけど、私が聞いても懐かしさに浸れるような気持ちになります。そしてひろしの回想で流れるアコースティックギターの曲と、しんのすけがタワーを登る時に流れるオーケストラの曲(曲名:21世紀を取り戻せ)が感情を増幅させました。
この映画は辻褄を追っていくと納得できるような内容ではないのですが、音楽と演技によって感情の流れが出来上がってると思うんですよね。
だから何度見てもしんのすけがタワー登るシーンで泣いてしまうわけです(笑)。
【設問1】
映画の尺が89分と短く、起承転結の『起』にかなりの時間を使っています。この映画の時間配分は良かったでしょうか?悪かったでしょうか?
→
一応ハリウッドの三幕構成で30/30/30分になってるからバランスがいいって解説してる人もいました。
けれど、私は最初見た時に20世紀博のシーン長いなーって思った記憶があります。
ただし、短い映画で満足感得られるのでそこは成功だなと思います。
【設問2】
この映画の主題として過去に生きるか、今を生きるかという問いがあります。今を生きる方を選ぶ根拠は、この映画の中で伝えきれていると思いますか?
→
過去の思い出の方が強く描写されているので、実は今を生きるってことについては描写が不足しているかなと感じます。
でもそれを補ってしまうほど音楽と演技が素晴らしかったと思います。
【設問3】
なぜこの子ども向けアニメーション映画が名作と言われていると思いますか?
→
なんか、不思議な映画ですよね(笑)。
コメディかと思ったらホラー、と思ったらラブロマンス、家族のヒューマンドラマ。
コメディは必ずしも笑えるわけではないし、最初は少し引いた目線でこの映画を見ると思うんです。
でも、しんのすけの両親がトラックの荷台に乗っているのを見て声を掛けるも無視される、しんのすけがひまわりを背負って家の縁石の上を走って手を振るあのシーンを観る頃に、魅入ってしまったなと気付きました。
粗のある作りではあるんですけど、この映画が名作と呼ばれる所以は、魂が感じられるからだと思います。
いい作品にしたいって現場の空気感がいい作画を引き出し、いい背景美術を引き出し、いい演技を引き出し、いい音楽を引き出すんじゃないかと思います。
返信
返信8
管
管理者さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:38 (No.1395850)削除課題映画、第22回映画好きの集い(新作)(2025年5月11日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
清
清水伸子さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:40削除「駆け出し女に駆け込み男」について
この映画は井上ひさしの小説「東慶寺花だより」を原作として原田真人が脚本、監督をつとめ2015年に公開された作品です。主演の大泉洋が第39回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、第58回ブルーリボン主演男優賞を満島ひかりが同じアカデミー賞優秀助演女優賞を受賞しています。
私は最初に観た時からこの映画の世界に引き込まれてしまいました。天保の時代の空気感、駆け込み寺東慶寺やその御用宿での様子や人間模様、脇を固める錚々たる役者たちなどこの映画の魅力は様々な所にあると思い今回の課題映画に選びました。
課題1.この映画を見終わった時の感想を教えてください
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
この映画は井上ひさしの小説「東慶寺花だより」を原作として原田真人が脚本、監督をつとめ2015年に公開された作品です。主演の大泉洋が第39回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、第58回ブルーリボン主演男優賞を満島ひかりが同じアカデミー賞優秀助演女優賞を受賞しています。
私は最初に観た時からこの映画の世界に引き込まれてしまいました。天保の時代の空気感、駆け込み寺東慶寺やその御用宿での様子や人間模様、脇を固める錚々たる役者たちなどこの映画の魅力は様々な所にあると思い今回の課題映画に選びました。
課題1.この映画を見終わった時の感想を教えてください
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
無
無敗の藤原さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:40削除【課題1】
この映画を見終わった時の感想を教えてください
→
稽古や仕事で女の人が生き生きとしているシーンが多くて、それがいいなぁって思いました。
それと、いたるシーンで自然を味わえるのもいいですよね。
【課題2】
印象に残った場面はどこでしょう
→
お吟に八犬伝を読み聞かせてるところですかね、よかったなぁとしみじみ感じました。
【課題3】
登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
→
捻りがないですけど、じょごさんです。
しんじろうと出会った当初の、何を見ても新しいというような目を丸くする表情も良かったですし、後半の芯が強い感じもいいですよね。
次点で馬琴先生も良かったです。そこに座っているだけで存在感があり、穏やかで重厚な空気を纏っていて凄い俳優さんだなと思いました。
【課題4】その他自由な感想ご意見をお願いします
→
八犬伝が完結するのか、早く最新刊が読みたい!っていうあの世界観が好きです。
小説を書く人がちゃんと尊敬されていて、批判する人がいて、作者には苦悩があってと、現代にも通じるそれが江戸時代にもあったのかもしれないと思うと嬉しいです。
この映画を見終わった時の感想を教えてください
→
稽古や仕事で女の人が生き生きとしているシーンが多くて、それがいいなぁって思いました。
それと、いたるシーンで自然を味わえるのもいいですよね。
【課題2】
印象に残った場面はどこでしょう
→
お吟に八犬伝を読み聞かせてるところですかね、よかったなぁとしみじみ感じました。
【課題3】
登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
→
捻りがないですけど、じょごさんです。
しんじろうと出会った当初の、何を見ても新しいというような目を丸くする表情も良かったですし、後半の芯が強い感じもいいですよね。
次点で馬琴先生も良かったです。そこに座っているだけで存在感があり、穏やかで重厚な空気を纏っていて凄い俳優さんだなと思いました。
【課題4】その他自由な感想ご意見をお願いします
→
八犬伝が完結するのか、早く最新刊が読みたい!っていうあの世界観が好きです。
小説を書く人がちゃんと尊敬されていて、批判する人がいて、作者には苦悩があってと、現代にも通じるそれが江戸時代にもあったのかもしれないと思うと嬉しいです。
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2025/2/27 10:07削除課題1.この映画を見終わった時の感想を教えてください
(回答)
冒頭は比較的退屈な印象だった。
セリフや言い回しが独特かつ早口な為、細かい内容が伝わってこなかったからかもしれない。
その為、途中で観るのをやめてしまった。それではいけないと思い、もう一度最初から観直してみた。
すると段々この独特な言い回しが耳に入ってきて、ストーリーが入ってくるようになった。そうなると俄然面白さが伝わってきた。
この映画は原作を読んでいる人にとってはそれを映像にしたことにより、より一層映像美が際立ったのではないだろうか?
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
(回答)
いくつかあります。
①冒頭、お吟(満島ひかり)を荷車に乗せて押しているじょご(戸田恵梨香)が追手に追われていると思い、追手をぶちのめし、草履を縁切り寺の境内に投げ入れるシーン。
②労咳にかかっているお吟が最期を迎えている時に、外で托鉢僧に姿を変えた堀切屋三郎衛門(堤真一)が、最後に彼女の死を扉の外から悼んでいたシーン。
③愛する人を想い想像妊娠する女に中村信次郎(大泉洋)がその事実を明らかにするシーン。
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
(回答)
中村信次郎役の大泉洋は軽妙で早台詞を言わせるのにはまり役であった。
だが、一番印象に残ったのはじょご役の戸田恵梨香である。
今までそんなに好きではなかったが、このじょご役で表情や役に合っており、好きになった。
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
(回答)
僕が一番好きなシーンは東慶寺内から外を映す雨の情景です。また苔に雨が当たり、穴をあけているシーンも印象的です。鎌倉が舞台であり、山、自然、そして寺がこんなにも美しく撮れている映画は観たことがありません。
監督の原田眞人は細部にまでこだわり、作り上げたという印象を持ちました。
いまほりさんにご紹介をいただき感謝しております。
(回答)
冒頭は比較的退屈な印象だった。
セリフや言い回しが独特かつ早口な為、細かい内容が伝わってこなかったからかもしれない。
その為、途中で観るのをやめてしまった。それではいけないと思い、もう一度最初から観直してみた。
すると段々この独特な言い回しが耳に入ってきて、ストーリーが入ってくるようになった。そうなると俄然面白さが伝わってきた。
この映画は原作を読んでいる人にとってはそれを映像にしたことにより、より一層映像美が際立ったのではないだろうか?
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
(回答)
いくつかあります。
①冒頭、お吟(満島ひかり)を荷車に乗せて押しているじょご(戸田恵梨香)が追手に追われていると思い、追手をぶちのめし、草履を縁切り寺の境内に投げ入れるシーン。
②労咳にかかっているお吟が最期を迎えている時に、外で托鉢僧に姿を変えた堀切屋三郎衛門(堤真一)が、最後に彼女の死を扉の外から悼んでいたシーン。
③愛する人を想い想像妊娠する女に中村信次郎(大泉洋)がその事実を明らかにするシーン。
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
(回答)
中村信次郎役の大泉洋は軽妙で早台詞を言わせるのにはまり役であった。
だが、一番印象に残ったのはじょご役の戸田恵梨香である。
今までそんなに好きではなかったが、このじょご役で表情や役に合っており、好きになった。
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
(回答)
僕が一番好きなシーンは東慶寺内から外を映す雨の情景です。また苔に雨が当たり、穴をあけているシーンも印象的です。鎌倉が舞台であり、山、自然、そして寺がこんなにも美しく撮れている映画は観たことがありません。
監督の原田眞人は細部にまでこだわり、作り上げたという印象を持ちました。
いまほりさんにご紹介をいただき感謝しております。
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2025/4/17 14:50削除「駆込み女と駆出し男」について
課題1.この映画を見終わった時の感想を教えてください
前半、セリフが小声やささやき声だったりして聞き取りにくく、設定もわかりにくく、なかなか世界に入って行けなかった。後半、女性たちが東慶寺に駆け込んでからは、展開がわかりやすくなった。駆け込みといっても、こんなに大変だったのかと思い、時代劇としてはちょっと異色の設定で、そこは興味深かった。
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
駆け込んだ女性たちに対し、男性が直接診察をできなかったということで、女性の目を借りて間接的に診察をするシーンが面白かった。
最後の方の寺の中での大立ち回りのシーン。女性たちが強かった。
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
一番は戸田恵梨香演じる、じょご。精神的にも肉体的にもその強さの表現に打たれた。各映画賞の助演女優賞はお吟役の満島ひかりが受賞したようだが、断然、戸田恵梨香の方が良かったと思う。大泉洋はいつもながら飄々としていて上手く、早口でもセリフが聞きとりやすい。だが監督の意向なのか、彼だけがお笑い的な演技をしている(させられている?)のが全体的なバランスとして少し気になった。
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
いま、NHKの『べらぼう』を観ている時期なので、それより少し後の時代なのかなあと思って観た。天保の質素倹約令で芝居や遊興が禁じられる。そんな息苦しい時代、女性から離縁を言い出すこともできず、その救いの手が鎌倉東慶寺にあった、という実際の歴史の一ページを観た思いがした。
課題1.この映画を見終わった時の感想を教えてください
前半、セリフが小声やささやき声だったりして聞き取りにくく、設定もわかりにくく、なかなか世界に入って行けなかった。後半、女性たちが東慶寺に駆け込んでからは、展開がわかりやすくなった。駆け込みといっても、こんなに大変だったのかと思い、時代劇としてはちょっと異色の設定で、そこは興味深かった。
課題2.印象に残った場面はどこでしょう
駆け込んだ女性たちに対し、男性が直接診察をできなかったということで、女性の目を借りて間接的に診察をするシーンが面白かった。
最後の方の寺の中での大立ち回りのシーン。女性たちが強かった。
課題3.登場人物の中で誰が一番印象的でしたか
一番は戸田恵梨香演じる、じょご。精神的にも肉体的にもその強さの表現に打たれた。各映画賞の助演女優賞はお吟役の満島ひかりが受賞したようだが、断然、戸田恵梨香の方が良かったと思う。大泉洋はいつもながら飄々としていて上手く、早口でもセリフが聞きとりやすい。だが監督の意向なのか、彼だけがお笑い的な演技をしている(させられている?)のが全体的なバランスとして少し気になった。
課題4.その他自由な感想ご意見をお願いします
いま、NHKの『べらぼう』を観ている時期なので、それより少し後の時代なのかなあと思って観た。天保の質素倹約令で芝居や遊興が禁じられる。そんな息苦しい時代、女性から離縁を言い出すこともできず、その救いの手が鎌倉東慶寺にあった、という実際の歴史の一ページを観た思いがした。
池
池内健さん (9inzq9ox)2025/5/6 12:29削除井上ひさしの原作「東慶寺花だより」を以前読んだことがあります。縁切り寺を願う女たちを扱った連作短編で、いろんな事情があるんだなという印象しか残っていませんでした。今回の映画は原作の複数のストーリーをたくみに組み合わせて一本の映画にまとめてあり、原作以上に印象深い作品になったと思います。
課題1.見終わった時の感想
戯作者志願の主人公は、井上ひさしの直木賞受賞作「手鎖心中」にも出てきて、江戸の滑稽本を深く分析して笑いを突き詰めた井上の思いを強く投影しています。この映画の主人公(狂言回し)を務める大泉洋は滑舌よくセリフをまくし立てて適役だと思いました。ただ、全般にセリフが難しく、字幕付きでみてようやく理解できました。映画館で見たら半分も分からなかったでしょう。
課題2.印象に残った場面
信次郎が薬草園に忍び込み、じょごにプロポーズする場面。見つからないかハラハラしました。
課題3.一番印象的な登場人物
法秀尼役の陽月華(ひづき・はな)。他の主要登場人物はだいたいどこかで見た顔でしたが、法秀尼は初見でした。あまり若くなくなじみのない美人女優が割と重要な役をやる場合は宝塚出身が多いと思って調べたら、やはり元宙組のトップ娘役でした。品のある役は、歌舞伎役者と宝塚OGだと安心してみられますね。
課題4.自由感想
信次郎は源兵衛のおいだが源兵衛は信次郎のおじではない、といって樹木希林が登場する場面は出落ちで面白い。宮﨑駿作品に出てくる預言者的な存在感がありました。
課題1.見終わった時の感想
戯作者志願の主人公は、井上ひさしの直木賞受賞作「手鎖心中」にも出てきて、江戸の滑稽本を深く分析して笑いを突き詰めた井上の思いを強く投影しています。この映画の主人公(狂言回し)を務める大泉洋は滑舌よくセリフをまくし立てて適役だと思いました。ただ、全般にセリフが難しく、字幕付きでみてようやく理解できました。映画館で見たら半分も分からなかったでしょう。
課題2.印象に残った場面
信次郎が薬草園に忍び込み、じょごにプロポーズする場面。見つからないかハラハラしました。
課題3.一番印象的な登場人物
法秀尼役の陽月華(ひづき・はな)。他の主要登場人物はだいたいどこかで見た顔でしたが、法秀尼は初見でした。あまり若くなくなじみのない美人女優が割と重要な役をやる場合は宝塚出身が多いと思って調べたら、やはり元宙組のトップ娘役でした。品のある役は、歌舞伎役者と宝塚OGだと安心してみられますね。
課題4.自由感想
信次郎は源兵衛のおいだが源兵衛は信次郎のおじではない、といって樹木希林が登場する場面は出落ちで面白い。宮﨑駿作品に出てくる預言者的な存在感がありました。
藤
藤野燦太郎さん (9ix0vf4z)2025/5/6 20:33削除駆け込み女と駆け出し男 感想 藤野燦太郎
いきなり映画を見たためなかなか難しくてついていけなかった。江戸時代の「縁切り制度」はこの幕府公認の縁切寺「東慶寺」に駆け込み、2~3年間尼となって修行すると、当時の法律で晴れて正式に縁切り(離婚)できるとのこと。自分はなかなか理解できず、前半はつらかったです。
1. 見終わったときの感想
現代の道徳で過去の人や制度を罰してはいけないものだが、理不尽な痛々しさがいくつも見られた。だが、駆け出しの見習い医者信次郎が、「戯作者になるため江戸に行くのならついていく」とじょごに言われ、江戸へ旅立つシーンで終わるのはよかった。
重い内容の作品だが、このシーンがあって救われた。鎌倉の東慶寺が尼寺であったことや縁切寺としての歴史、その縁切り制度詳細を調べて初めてつながって、この感想が書けた次第です。
2. 印象に残るシーン
この江戸時代を題材にした映画なのに、現代のメンタルクリニックを見ているようなシーンがあった。
おゆきの想像妊娠のシーン
おゆきは、実家の相模屋に入った夫の徳治が、酒癖の悪いばくち打ちであることに悩んでいた。実家は離縁させたくて、おゆきは東慶寺に入ることになった。しかしおゆきは今おめでたのようにふるまっている。これはおゆきが実家の言いなりになって東慶寺に入ったが、納得しているわけでなく、徳治に未練があり妊娠すれば離縁しなくてよくなると体が反応しているだけだ、と信次郎は判断して大審問で皆の前でおゆきに言う。
「あなたは子を宿すことはできないのです。痛いと言い聞かせてるだけなんだよ、あんたは! うその痛みで自分を罰することはないんですよ、おゆきさん」
妊娠に対する強い期待がある場合、お乳が張ったり、おなかが張ったり、つわり症状などが起こるようです。もちろん妊娠したくないと強く思っている人にも起こるようです。女性の方々がよくご存じですよね。
3. 印象に残る人物
信次郎役大泉洋は軽めの印象が現代人を引き込むうえで必要と思われた。しかし三代目柏谷源兵衛役の樹木希林は物語の重しになっているようで、軽めの信次郎をカバーしてくれてよかったです。
今回このような奥深い作品を選んでいただきありがとうございました。
東慶寺は今は一般のお寺になっているようですが、鎌倉にあるのでそのうちに行ってみようと思います。
いきなり映画を見たためなかなか難しくてついていけなかった。江戸時代の「縁切り制度」はこの幕府公認の縁切寺「東慶寺」に駆け込み、2~3年間尼となって修行すると、当時の法律で晴れて正式に縁切り(離婚)できるとのこと。自分はなかなか理解できず、前半はつらかったです。
1. 見終わったときの感想
現代の道徳で過去の人や制度を罰してはいけないものだが、理不尽な痛々しさがいくつも見られた。だが、駆け出しの見習い医者信次郎が、「戯作者になるため江戸に行くのならついていく」とじょごに言われ、江戸へ旅立つシーンで終わるのはよかった。
重い内容の作品だが、このシーンがあって救われた。鎌倉の東慶寺が尼寺であったことや縁切寺としての歴史、その縁切り制度詳細を調べて初めてつながって、この感想が書けた次第です。
2. 印象に残るシーン
この江戸時代を題材にした映画なのに、現代のメンタルクリニックを見ているようなシーンがあった。
おゆきの想像妊娠のシーン
おゆきは、実家の相模屋に入った夫の徳治が、酒癖の悪いばくち打ちであることに悩んでいた。実家は離縁させたくて、おゆきは東慶寺に入ることになった。しかしおゆきは今おめでたのようにふるまっている。これはおゆきが実家の言いなりになって東慶寺に入ったが、納得しているわけでなく、徳治に未練があり妊娠すれば離縁しなくてよくなると体が反応しているだけだ、と信次郎は判断して大審問で皆の前でおゆきに言う。
「あなたは子を宿すことはできないのです。痛いと言い聞かせてるだけなんだよ、あんたは! うその痛みで自分を罰することはないんですよ、おゆきさん」
妊娠に対する強い期待がある場合、お乳が張ったり、おなかが張ったり、つわり症状などが起こるようです。もちろん妊娠したくないと強く思っている人にも起こるようです。女性の方々がよくご存じですよね。
3. 印象に残る人物
信次郎役大泉洋は軽めの印象が現代人を引き込むうえで必要と思われた。しかし三代目柏谷源兵衛役の樹木希林は物語の重しになっているようで、軽めの信次郎をカバーしてくれてよかったです。
今回このような奥深い作品を選んでいただきありがとうございました。
東慶寺は今は一般のお寺になっているようですが、鎌倉にあるのでそのうちに行ってみようと思います。
上
上終結城さん (8g07wmfj)2025/5/7 10:37削除【課題1】この映画を見終わった時の感想を教えてください。
【回答1】
やむにやまれず東慶寺に駆け込んできた女性たち、そのエピソードを巧みに取り入れて、エンタメ作品に仕上げている。現在、井上ひさしの『東慶寺だより』を4/5(残り約百頁)ほど読んでいるが、映画では原作にない要素をかなり自由に創作している(脚本は原田眞人)。たとえば、お吟(満島ひかり)の旦那で、じつは凄腕の盗賊団の頭領、堀切屋三郎衛門(堤真一)のエピソードは原作にはない。だから映画的な見せ場である盗賊団の捕り物(アクションシーン)や、お吟の死の床の近くで托鉢に化けた堀切屋が立って読経するシーン、などは映画だけの創作である。
信次郎は戯作者志望であると同時に、医者見習いでもある。新米医者がさまざまな患者を診る経験を積みながら成長してゆく物語、これは山本周五郎の『赤ひげ診療譚』とこれを原作にした黒澤明の『赤ひげ』(1965)を彷彿させた。ただし映画『駆込み女と駆出し男』は、井上ひさしの原作に寄せて、よほどユーモラスな味になっている。
【課題2】印象に残った場面はどこでしょう。
【回答2】
(1)労咳(肺結核)で死期が迫ったお吟が、信次郎に背負われて東慶寺を出てゆく場面。お吟がじょごに背中を向けながら「わたしの妹、べったべった、だんだん(いつもいつもありがとう)」と言って手を振るシーン、ここは泣けた。
(2)じょごが、長崎行きは断るが江戸にならついて行く、と信次郎の求愛を受け入れる場面。コミカルな中に情愛があふれるラブシーンだった。
【課題3】登場人物の中で誰が一番印象的でしたか。
【回答3】
(1)映画を先に観たせいで、あとから原作を読むと信次郎がどうしても大泉洋の顔になってしまう。それほど大泉のユーモラスなキャラクターがぴったりハマった役、演技だった。もしこの信次郎を別の俳優が演じるとすれば誰だろう? コミカルな味も出せる堺雅人などが浮かぶ。しかし大泉とはかなり違う信次郎になっただろう。
(2)原作『東慶寺だより』では、御用宿の主人柏屋源兵衛が女とはなっていない。しかし、駆け込み女の心情を深く理解し助けようとする源兵衛を、樹木希林に演じさせたのは、いいアイデアだったと思う。
(3)柏屋の番頭夫婦(利平とお勝)と信次郎たちのとぼけたやり取り、とくにお勝(キムラ緑子)の表情やしぐさがなんとも可笑しい。
【課題4】その他自由な感想ご意見をお願いします。
【自由感想】
江戸時代の「駆け込み寺」という制度が、実際どのように運用され機能していたのか、この映画で初めて知った。原作にも説明はあるのだが、映画の前半、御用宿で駆け込み寺の制度、仕組みを説明する場面があり、映画の方がわかりやすかった。女性が弱い立場だったこの時代に、公的な女性救済制度があったことに驚かされる。
【回答1】
やむにやまれず東慶寺に駆け込んできた女性たち、そのエピソードを巧みに取り入れて、エンタメ作品に仕上げている。現在、井上ひさしの『東慶寺だより』を4/5(残り約百頁)ほど読んでいるが、映画では原作にない要素をかなり自由に創作している(脚本は原田眞人)。たとえば、お吟(満島ひかり)の旦那で、じつは凄腕の盗賊団の頭領、堀切屋三郎衛門(堤真一)のエピソードは原作にはない。だから映画的な見せ場である盗賊団の捕り物(アクションシーン)や、お吟の死の床の近くで托鉢に化けた堀切屋が立って読経するシーン、などは映画だけの創作である。
信次郎は戯作者志望であると同時に、医者見習いでもある。新米医者がさまざまな患者を診る経験を積みながら成長してゆく物語、これは山本周五郎の『赤ひげ診療譚』とこれを原作にした黒澤明の『赤ひげ』(1965)を彷彿させた。ただし映画『駆込み女と駆出し男』は、井上ひさしの原作に寄せて、よほどユーモラスな味になっている。
【課題2】印象に残った場面はどこでしょう。
【回答2】
(1)労咳(肺結核)で死期が迫ったお吟が、信次郎に背負われて東慶寺を出てゆく場面。お吟がじょごに背中を向けながら「わたしの妹、べったべった、だんだん(いつもいつもありがとう)」と言って手を振るシーン、ここは泣けた。
(2)じょごが、長崎行きは断るが江戸にならついて行く、と信次郎の求愛を受け入れる場面。コミカルな中に情愛があふれるラブシーンだった。
【課題3】登場人物の中で誰が一番印象的でしたか。
【回答3】
(1)映画を先に観たせいで、あとから原作を読むと信次郎がどうしても大泉洋の顔になってしまう。それほど大泉のユーモラスなキャラクターがぴったりハマった役、演技だった。もしこの信次郎を別の俳優が演じるとすれば誰だろう? コミカルな味も出せる堺雅人などが浮かぶ。しかし大泉とはかなり違う信次郎になっただろう。
(2)原作『東慶寺だより』では、御用宿の主人柏屋源兵衛が女とはなっていない。しかし、駆け込み女の心情を深く理解し助けようとする源兵衛を、樹木希林に演じさせたのは、いいアイデアだったと思う。
(3)柏屋の番頭夫婦(利平とお勝)と信次郎たちのとぼけたやり取り、とくにお勝(キムラ緑子)の表情やしぐさがなんとも可笑しい。
【課題4】その他自由な感想ご意見をお願いします。
【自由感想】
江戸時代の「駆け込み寺」という制度が、実際どのように運用され機能していたのか、この映画で初めて知った。原作にも説明はあるのだが、映画の前半、御用宿で駆け込み寺の制度、仕組みを説明する場面があり、映画の方がわかりやすかった。女性が弱い立場だったこの時代に、公的な女性救済制度があったことに驚かされる。
返信
返信7
管
管理者さん (8pa6wkw7)2025/2/25 08:52 (No.1395865)削除第22回文横映画好きの集い(自由映画)(2025年5月11日)について、ご自由に感想をお書込みください!
返信
返信0
管
管理者さん (8pa6wkw7)2024/11/18 14:25 (No.1328942)削除課題映画、第21回映画好きの集い(新作)(2025年2月9日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2024/11/22 15:11削除今回新作映画担当という事で、まだ観たことは無かったが、観てみたいと思っていた『ザ・ホエール』を選んでみた。
『ザ・ホエール』は、2022年のアメリカ合衆国のドラマ映画。 劇作家サミュエル・D・ハンターが2012年に発表した同名舞台劇を映画化。ダーレン・アロノフスキー監督、ブレンダン・フレイザー主演。
テーマは以下の4つです。忌憚のないご意見をお待ちしております。
【テーマ】
①本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
②リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
③ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
④自由に感想をお願いします。
『ザ・ホエール』は、2022年のアメリカ合衆国のドラマ映画。 劇作家サミュエル・D・ハンターが2012年に発表した同名舞台劇を映画化。ダーレン・アロノフスキー監督、ブレンダン・フレイザー主演。
テーマは以下の4つです。忌憚のないご意見をお待ちしております。
【テーマ】
①本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
②リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
③ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
④自由に感想をお願いします。
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2024/12/4 09:12削除この映画を初めて観たわけですが、なかなかいい映画だと思いました。
客観的に観ると、妻と娘を捨て、愛する男に走った身勝手なゲイの話であるが、彼の人間性を見るにつけ、正直さであったり、優しさが垣間見れ、人間とは?という本質に迫っている映画であると思う。
以下に自分なりのテーマに対する感想を述べたいと思う。
①本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
⇒本映画、様々なテーマがあった。その中でもHonest(正直)がこの映画の一番訴えたかった内容であると思う。
チャーリーは自分の正直な気持ちに従って、アランとの愛にのめり込んでしまった。結果妻と娘を不幸にしてしまうわけだが、その選択を彼は後悔していない。
死を意識し、今度は娘に「Honest(正直)」を悟ってもらう事を自分の人生の最後の目標にしたのだと思う。
②リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
⇒チャーリーがゲイでなかったら、好きになっていたんだと思う。
矢印がリズ⇒チャーリー⇒アラン
と向いている。
③ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
⇒お願いだから、生きるのをあきらめないで! という娘が父親に一日でも長く生きていて!と言う正直な思いを口にできたのだと思う。
まだ私の為に生きていて頂戴と言うpleasu!だったんだと思う。
④自由に感想をお願いします。
⇒自分の死を覚悟した時に、やり残していたこと、悔いが残っている事を自問自答した時、チャーリーは8歳の時に置いて出てきた娘の事を思い出す。
死ぬ前に、娘に会って謝りたい、金を残してある旨を伝えたいと思う。
ストーリー全体に漂っているのは、娘エリーが何年か前に書いたメルヴィルの『白鯨』に関してのエッセイである。
チャーリーはこの娘のエッセイを何度も何度も読み返しては、自分自身への罪と娘に対しての贖罪の気持ちを思い出していた。
本映画は登場人物が最少人数で、その登場人物はチャーリーの家に集まってきて、会話をする。
まさしく舞台劇のような構成映画である。これは元々舞台劇であったため、映画でもその名残が出ている。
おかしな話、出ては消え、消えては出て、ほとんど全員がバッティングすることは無い。
それぞれが自らの役回りをこなし、テーマを与えていく。
チャーリーはそのテーマに対して苦悩したり、打ちのめされたりするが、一貫していることは、愛に正直に生きているという事である。
ダメなチャーリーであるが、憎めない存在である。
娘に罵倒され、宿題を手伝い、金を与えると言い、一見だらしのないダメオヤジであるが、娘エリーの為に絶対にめげたりしない。
最後、エリーの為にわざとちゃんとしたレポートを書かずに、エリーが書いた白鯨の感想をアレンジしたものを渡し、彼女にそれを読ませる。
お前には才能があるという事を父親としてちゃんと理解できていることを示したかったのだと思う。そしてそれだけはちゃんと伝えたかったのだと思う。
エリーもまた初めて嫌いでならなかった自分自身と向き合えたのだと思える瞬間である。
チャーリー自身がイエス・キリストだと思える演出が随所にある。
映画は月曜日から始まり金曜日に終わる。5日間の物語である。
キリストの最期の5日間になぞらえているという気もする。
木曜日の夜に狂ったように食事をとる。それが最後の晩餐だったと考えられなくもない。
様々なテーマが内包された映画であるが、そして主人公が過食症により272kgという大巨漢であり、身動き一つ取るのも人の手を煩わせる迷惑な感じであるが、彼の憎めない性格が人を集め、彼の死を悼んだのは間違いない。
最後にメークに4時間を掛けた、ブレンダン・フレイザーの272Kgの大巨漢があまりにもリアル過ぎた。
客観的に観ると、妻と娘を捨て、愛する男に走った身勝手なゲイの話であるが、彼の人間性を見るにつけ、正直さであったり、優しさが垣間見れ、人間とは?という本質に迫っている映画であると思う。
以下に自分なりのテーマに対する感想を述べたいと思う。
①本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
⇒本映画、様々なテーマがあった。その中でもHonest(正直)がこの映画の一番訴えたかった内容であると思う。
チャーリーは自分の正直な気持ちに従って、アランとの愛にのめり込んでしまった。結果妻と娘を不幸にしてしまうわけだが、その選択を彼は後悔していない。
死を意識し、今度は娘に「Honest(正直)」を悟ってもらう事を自分の人生の最後の目標にしたのだと思う。
②リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
⇒チャーリーがゲイでなかったら、好きになっていたんだと思う。
矢印がリズ⇒チャーリー⇒アラン
と向いている。
③ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
⇒お願いだから、生きるのをあきらめないで! という娘が父親に一日でも長く生きていて!と言う正直な思いを口にできたのだと思う。
まだ私の為に生きていて頂戴と言うpleasu!だったんだと思う。
④自由に感想をお願いします。
⇒自分の死を覚悟した時に、やり残していたこと、悔いが残っている事を自問自答した時、チャーリーは8歳の時に置いて出てきた娘の事を思い出す。
死ぬ前に、娘に会って謝りたい、金を残してある旨を伝えたいと思う。
ストーリー全体に漂っているのは、娘エリーが何年か前に書いたメルヴィルの『白鯨』に関してのエッセイである。
チャーリーはこの娘のエッセイを何度も何度も読み返しては、自分自身への罪と娘に対しての贖罪の気持ちを思い出していた。
本映画は登場人物が最少人数で、その登場人物はチャーリーの家に集まってきて、会話をする。
まさしく舞台劇のような構成映画である。これは元々舞台劇であったため、映画でもその名残が出ている。
おかしな話、出ては消え、消えては出て、ほとんど全員がバッティングすることは無い。
それぞれが自らの役回りをこなし、テーマを与えていく。
チャーリーはそのテーマに対して苦悩したり、打ちのめされたりするが、一貫していることは、愛に正直に生きているという事である。
ダメなチャーリーであるが、憎めない存在である。
娘に罵倒され、宿題を手伝い、金を与えると言い、一見だらしのないダメオヤジであるが、娘エリーの為に絶対にめげたりしない。
最後、エリーの為にわざとちゃんとしたレポートを書かずに、エリーが書いた白鯨の感想をアレンジしたものを渡し、彼女にそれを読ませる。
お前には才能があるという事を父親としてちゃんと理解できていることを示したかったのだと思う。そしてそれだけはちゃんと伝えたかったのだと思う。
エリーもまた初めて嫌いでならなかった自分自身と向き合えたのだと思える瞬間である。
チャーリー自身がイエス・キリストだと思える演出が随所にある。
映画は月曜日から始まり金曜日に終わる。5日間の物語である。
キリストの最期の5日間になぞらえているという気もする。
木曜日の夜に狂ったように食事をとる。それが最後の晩餐だったと考えられなくもない。
様々なテーマが内包された映画であるが、そして主人公が過食症により272kgという大巨漢であり、身動き一つ取るのも人の手を煩わせる迷惑な感じであるが、彼の憎めない性格が人を集め、彼の死を悼んだのは間違いない。
最後にメークに4時間を掛けた、ブレンダン・フレイザーの272Kgの大巨漢があまりにもリアル過ぎた。
無
無敗の藤原さん (95c8u6fd)2025/1/2 14:27削除【設問1】
本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
→
正直、が一番のテーマだと思います。多種多様な人物の、その背景は違えど共通して何かを隠して生きているように思います。(娘は正直な人の象徴)
【設問2】
リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
→
愛情のように見えましたね。女の人がゲイの人を好きになるってことは、ジェンダーの世界を想像するにかなり稀だと思います。
【設問3】
ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
→
死なないでってことを言いたかったように思えます。
やっと和解できるかもというときに、チャーリーの死期が迫っていて、言葉にならない言葉という感じがしていいセリフだなと思いました。
【設問4】
自由に感想をお願いします。
→
この映画の主人公は一言で言うと惨め。その惨めさをこれでもかっていうくらいリアルに映して、その印象を最終的には変わることになりましたね。
全体的に見易く、引き込まれる映画となっているものの、過食のシーンなんかは正直目を覆いたくなる…。
この映画で何度も主人公が言おうとしてた、本当の言葉に価値があるって考え方は共感できます。
そして、後半の奥さんとの会話で、自分が死ぬ前に希望を持たせてくれという切実な願いに胸を打たれた。やっぱり人間というのは未来を見る生き物なんだなと感じました。
本映画は「白鯨」、「新興宗教(聖書)」、「ゲイ(同性愛)」、「過食、うっ血性心不全」、「邪悪な子」「Honest(正直)」などのテーマが織り込まれていますが、 一番のテーマは何だと思いますか?※上記以外でも可
→
正直、が一番のテーマだと思います。多種多様な人物の、その背景は違えど共通して何かを隠して生きているように思います。(娘は正直な人の象徴)
【設問2】
リズのチャーリーに対する感情は、友情ですか? それとも愛情だと思いますか?
→
愛情のように見えましたね。女の人がゲイの人を好きになるってことは、ジェンダーの世界を想像するにかなり稀だと思います。
【設問3】
ラスト、娘のエリーが「Daddy Please!」と叫ぶシーンがありますが、何をお願いしたと思いますか?
→
死なないでってことを言いたかったように思えます。
やっと和解できるかもというときに、チャーリーの死期が迫っていて、言葉にならない言葉という感じがしていいセリフだなと思いました。
【設問4】
自由に感想をお願いします。
→
この映画の主人公は一言で言うと惨め。その惨めさをこれでもかっていうくらいリアルに映して、その印象を最終的には変わることになりましたね。
全体的に見易く、引き込まれる映画となっているものの、過食のシーンなんかは正直目を覆いたくなる…。
この映画で何度も主人公が言おうとしてた、本当の言葉に価値があるって考え方は共感できます。
そして、後半の奥さんとの会話で、自分が死ぬ前に希望を持たせてくれという切実な願いに胸を打たれた。やっぱり人間というのは未来を見る生き物なんだなと感じました。
上
上終結城さん (8g07wmfj)2025/2/3 23:35削除1.はじめに
本作『ザ・ホエール』は初見。主演のブレンダン・フレイザーがアカデミー賞(主演男優賞)を受賞したので一応録画していたが、この機会に鑑賞することができた。
全編のほとんどが主人公チャーリーの住む暗い部屋の中。原作が舞台劇だったのもうなずける。車椅子の主人公が部屋から出られない設定は、ヒッチコックの『裏窓』を思い出させるが、この映画では、主人公の視界は部屋の内側にほぼ限定されている。そして映画の背景に流れる音楽は、海の中で聞く鯨の鳴き声のよう。おそらくこの舞台設定は旧約聖書『ヨナ書』の物語をイメージしている。(イスラエルの預言者ヨナが神の怒りにふれ海で遭難、大きな魚(鯨)に飲み込まれて、三日三晩、魚の体内に閉じ込められる。)
2.課題について
【課題1】一番のテーマは何だと思いますか?
【回答1】
死を目前にしたチャーリーの「和解」がテーマだと思う。和解の相手は①娘エリー、②妻メアリー、③看護師リズ。チャーリーは恋人アラン(リズの兄)と一緒になるために妻と娘を捨てた。またリズは、兄の死の原因となったチャーリーを恨んでいてもおかしくない。
もちろん完全な「和解」が得られるはずもないが、チャーリーは彼らと、ひとときだけでももう一度心を通わせることができた。たとえば妻メアリーはチャーリーの苦しそうな呼吸音を、彼の胸に顔をうずめて聴く。そして楽しかった家族三人での海水浴の思い出を語る。
もうひとつ、本作の中には、ニューライフなるキリスト教系新興宗教の偽伝道師の青年(トーマス)が登場する。この青年はチャーリーへの伝道(魂の救済)には失敗するが、娘エリーの仕業(?)により、結果として親元へ帰ることができた。これも、もう一つの和解だろう。福音書の「放蕩息子」のエピソードを連想させる。
【課題2】リズのチャーリーに対する感情は、友情? 愛情?
【回答2】
男女の愛情とは違うが、人間どうしの愛情だと思う。リズはチャーリーが心の優しい人間であることを理解している。また看護師として患者に抱く親愛の情もあるだろう。そして、兄が愛した人、おそらく兄の自殺の原因になった人に対する複雑な感情があったはずだ。
【課題3】娘エリーの「Daddy Please! 」は何をお願いしたのか?
【回答3】
すなおに「死なないで!」の叫びだと思う。妻メアリーはチャーリーにこう言う、エリーは母娘を捨てたあなたを憎む態度をとっているが、本当は「あなたが好きなのだ。」
3.その他
偽伝道師トーマスの言葉は、うわすべりして少しもチャーリーの心に響かない。この青年の空疎な伝道の挿話は、この映画にとってどんな意味があるのか、すこし疑問だ。ただ『ヨナ書』を連想させる設定や放蕩息子などのキリスト教的な雰囲気は、欧米人になじみのあるものなのだろう。ちなみにヨナ書のテーマは、異邦人(ユダヤ人以外)に対する神の救い。
本作『ザ・ホエール』は初見。主演のブレンダン・フレイザーがアカデミー賞(主演男優賞)を受賞したので一応録画していたが、この機会に鑑賞することができた。
全編のほとんどが主人公チャーリーの住む暗い部屋の中。原作が舞台劇だったのもうなずける。車椅子の主人公が部屋から出られない設定は、ヒッチコックの『裏窓』を思い出させるが、この映画では、主人公の視界は部屋の内側にほぼ限定されている。そして映画の背景に流れる音楽は、海の中で聞く鯨の鳴き声のよう。おそらくこの舞台設定は旧約聖書『ヨナ書』の物語をイメージしている。(イスラエルの預言者ヨナが神の怒りにふれ海で遭難、大きな魚(鯨)に飲み込まれて、三日三晩、魚の体内に閉じ込められる。)
2.課題について
【課題1】一番のテーマは何だと思いますか?
【回答1】
死を目前にしたチャーリーの「和解」がテーマだと思う。和解の相手は①娘エリー、②妻メアリー、③看護師リズ。チャーリーは恋人アラン(リズの兄)と一緒になるために妻と娘を捨てた。またリズは、兄の死の原因となったチャーリーを恨んでいてもおかしくない。
もちろん完全な「和解」が得られるはずもないが、チャーリーは彼らと、ひとときだけでももう一度心を通わせることができた。たとえば妻メアリーはチャーリーの苦しそうな呼吸音を、彼の胸に顔をうずめて聴く。そして楽しかった家族三人での海水浴の思い出を語る。
もうひとつ、本作の中には、ニューライフなるキリスト教系新興宗教の偽伝道師の青年(トーマス)が登場する。この青年はチャーリーへの伝道(魂の救済)には失敗するが、娘エリーの仕業(?)により、結果として親元へ帰ることができた。これも、もう一つの和解だろう。福音書の「放蕩息子」のエピソードを連想させる。
【課題2】リズのチャーリーに対する感情は、友情? 愛情?
【回答2】
男女の愛情とは違うが、人間どうしの愛情だと思う。リズはチャーリーが心の優しい人間であることを理解している。また看護師として患者に抱く親愛の情もあるだろう。そして、兄が愛した人、おそらく兄の自殺の原因になった人に対する複雑な感情があったはずだ。
【課題3】娘エリーの「Daddy Please! 」は何をお願いしたのか?
【回答3】
すなおに「死なないで!」の叫びだと思う。妻メアリーはチャーリーにこう言う、エリーは母娘を捨てたあなたを憎む態度をとっているが、本当は「あなたが好きなのだ。」
3.その他
偽伝道師トーマスの言葉は、うわすべりして少しもチャーリーの心に響かない。この青年の空疎な伝道の挿話は、この映画にとってどんな意味があるのか、すこし疑問だ。ただ『ヨナ書』を連想させる設定や放蕩息子などのキリスト教的な雰囲気は、欧米人になじみのあるものなのだろう。ちなみにヨナ書のテーマは、異邦人(ユダヤ人以外)に対する神の救い。
池
池内健さん (9fbmysza)2025/2/4 10:35削除①本映画のテーマ
正直に生きることの大切さ。それが結果的に(精神的な)幸せにつながる。エリーのことを母親は「邪悪だ」というが父親(チャーリー)は「正直なだけだ」と言って信じる。同じことをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかというコントラストでもある。宣教師のトーマスがエリーによって悪事を暴露されながらもそれがきっかけとなって家族の元に帰ることができたのは聖書からのモチーフとしてフィクションによく用いられる「放蕩息子の帰還」だろう。
②リズのチャーリーに対する感情
同志愛。愛する者を失った者同士の共感。恋愛感情はないと思う。
③エリーの願い
救急車を呼んで病院に行くこと。しかし、それはすでに手遅れであること、また、チャーリーの願いは「長く生きる」ではなく「よく生きる(よく死ぬ)」であることを理解し、父の言葉にしたがって朗読を始める。これが救いとなってチャーリーは懺悔の末、笑顔で天に昇る(死ぬ)ことができた。ハッピーエンドだと受け止めた。
③自由感想
全編がキリスト教的なモチーフに貫かれている。どんなにタブー(同性愛、離婚、貪欲)を破っても最後に改心すれば救われる、と教え導くPRビデオのように見えてしまった。チャーリーが昇天するとき、長年看護に携わりながらキリスト教(系新興宗教)に忌避感を持つリズが席を外していたのが象徴的だ。
「ザ・ホエール」というタイトル通り、繰り返し登場する「白鯨」は、過食(緩慢な自殺)によって巨体になってしまったチャーリー自身なのだろう。自分で自分をコントロールできず(精神的に)さまようだけ。そして、その白鯨を殺すことが人生の目的となっているエイハブ船長も、(別の男と同宿する=同性愛を示唆される)語り手のイシュメイルもチャーリー自身。1人3役で暗鬱な「白鯨」の世界を演じている。
正直に生きることの大切さ。それが結果的に(精神的な)幸せにつながる。エリーのことを母親は「邪悪だ」というが父親(チャーリー)は「正直なだけだ」と言って信じる。同じことをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかというコントラストでもある。宣教師のトーマスがエリーによって悪事を暴露されながらもそれがきっかけとなって家族の元に帰ることができたのは聖書からのモチーフとしてフィクションによく用いられる「放蕩息子の帰還」だろう。
②リズのチャーリーに対する感情
同志愛。愛する者を失った者同士の共感。恋愛感情はないと思う。
③エリーの願い
救急車を呼んで病院に行くこと。しかし、それはすでに手遅れであること、また、チャーリーの願いは「長く生きる」ではなく「よく生きる(よく死ぬ)」であることを理解し、父の言葉にしたがって朗読を始める。これが救いとなってチャーリーは懺悔の末、笑顔で天に昇る(死ぬ)ことができた。ハッピーエンドだと受け止めた。
③自由感想
全編がキリスト教的なモチーフに貫かれている。どんなにタブー(同性愛、離婚、貪欲)を破っても最後に改心すれば救われる、と教え導くPRビデオのように見えてしまった。チャーリーが昇天するとき、長年看護に携わりながらキリスト教(系新興宗教)に忌避感を持つリズが席を外していたのが象徴的だ。
「ザ・ホエール」というタイトル通り、繰り返し登場する「白鯨」は、過食(緩慢な自殺)によって巨体になってしまったチャーリー自身なのだろう。自分で自分をコントロールできず(精神的に)さまようだけ。そして、その白鯨を殺すことが人生の目的となっているエイハブ船長も、(別の男と同宿する=同性愛を示唆される)語り手のイシュメイルもチャーリー自身。1人3役で暗鬱な「白鯨」の世界を演じている。
清
清水伸子さん (8p590r59)2025/2/5 17:00削除課題1.一番のテーマはなんだと思いますか?
正直なありのままの心で生きる事の大切さと,人が奥底に持っている善なるものへの肯定だと思いました.
課題2.リズのチャーリーに対する感情は?
友情であり,家族愛に近いように思いました.
課題3.最後のエリーの言葉は何を願ったのでしょうか?
憎んでいたはずの父親だったが,彼が丸ごと自分を肯定し愛していることを感じ取って,生きて欲しいと心から願った言葉だったように思います.
課題4.自由感想
チャーリーは悍ましいと表現されるほど太っているけれど,彼の声は深みがある。その言葉からは,彼の繊細で優しい心が伝わってくる.だからこそ,一度彼と深く知り合ったリズや元妻,そして娘のエリーも最後には彼を許し,心を通わせるのではないかと思いました.みんなに去られた後、油まみれになって食べ物を口に押し込む様子は、多分最愛の人アランを失った後の彼の姿だと感じました.過食は彼のどうしようもなく悲しむ姿なのだと.彼は悲しみを自分の中に溜め込み、決して怒りとして外に人に向けようとはしません.トーマスに「悍ましいか?」と詰め寄るのも彼に本当の言葉を引き出すためだったのではないでしょうか?醜く見える彼の巨体の中に私は限りない優しさを感じました.とても好きな映画でした、ありがとうございました.
正直なありのままの心で生きる事の大切さと,人が奥底に持っている善なるものへの肯定だと思いました.
課題2.リズのチャーリーに対する感情は?
友情であり,家族愛に近いように思いました.
課題3.最後のエリーの言葉は何を願ったのでしょうか?
憎んでいたはずの父親だったが,彼が丸ごと自分を肯定し愛していることを感じ取って,生きて欲しいと心から願った言葉だったように思います.
課題4.自由感想
チャーリーは悍ましいと表現されるほど太っているけれど,彼の声は深みがある。その言葉からは,彼の繊細で優しい心が伝わってくる.だからこそ,一度彼と深く知り合ったリズや元妻,そして娘のエリーも最後には彼を許し,心を通わせるのではないかと思いました.みんなに去られた後、油まみれになって食べ物を口に押し込む様子は、多分最愛の人アランを失った後の彼の姿だと感じました.過食は彼のどうしようもなく悲しむ姿なのだと.彼は悲しみを自分の中に溜め込み、決して怒りとして外に人に向けようとはしません.トーマスに「悍ましいか?」と詰め寄るのも彼に本当の言葉を引き出すためだったのではないでしょうか?醜く見える彼の巨体の中に私は限りない優しさを感じました.とても好きな映画でした、ありがとうございました.
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2025/2/6 16:32削除「ザ・ホエール」を観て
1. この作品の一番のテーマは?
人間愛、親子愛、そのために自分に正直であれということだろうか。
2. リズのチャーリーに対する感情は?
リズにとって愛する兄とのつながりがあったチャーリー。思い出を分かち合う上でも大切な存在であり、その気持ちは愛情に近かったと思う。
3. ラストで娘のエリーが「ダディ、プリーズ」と叫ぶが何をお願いした?
「生きて、お願い」という素直で正直な気持ちだろう。
4. 自由感想は?
ずっとチャーリーの部屋の中だけの場面なのに飽きさせなかった。舞台劇っぽいな、と思っていたのだが、実際に舞台劇が原作のようだ。
それにしてもチャーリー役のブレンダン・フレイザーの演技が凄い。演技の前にまず、そのクジラのような体躯に圧倒される。これがファット・スーツと特殊メイクだというのだから驚きだ。その体躯を持て余すような病的なチャーリーの動きや生活状態に、非現実的ではあるが見入ってしまった。普通なら病院に行くだろう。だがその費用も惜しんで娘に残したかったのか。そのあたりはちょっと疑問が残る。言わば、ソフトな自殺行為だからだ。
ちなみに主演のブレンダン・フレイザーで検索してみたら、過去の映画で『ジャングル・ジョージ』というのがあって、ものすごくイケメンで細マッチョというか筋肉隆々なので、この映画とのギャップに超びっくりしてしまった!!
1. この作品の一番のテーマは?
人間愛、親子愛、そのために自分に正直であれということだろうか。
2. リズのチャーリーに対する感情は?
リズにとって愛する兄とのつながりがあったチャーリー。思い出を分かち合う上でも大切な存在であり、その気持ちは愛情に近かったと思う。
3. ラストで娘のエリーが「ダディ、プリーズ」と叫ぶが何をお願いした?
「生きて、お願い」という素直で正直な気持ちだろう。
4. 自由感想は?
ずっとチャーリーの部屋の中だけの場面なのに飽きさせなかった。舞台劇っぽいな、と思っていたのだが、実際に舞台劇が原作のようだ。
それにしてもチャーリー役のブレンダン・フレイザーの演技が凄い。演技の前にまず、そのクジラのような体躯に圧倒される。これがファット・スーツと特殊メイクだというのだから驚きだ。その体躯を持て余すような病的なチャーリーの動きや生活状態に、非現実的ではあるが見入ってしまった。普通なら病院に行くだろう。だがその費用も惜しんで娘に残したかったのか。そのあたりはちょっと疑問が残る。言わば、ソフトな自殺行為だからだ。
ちなみに主演のブレンダン・フレイザーで検索してみたら、過去の映画で『ジャングル・ジョージ』というのがあって、ものすごくイケメンで細マッチョというか筋肉隆々なので、この映画とのギャップに超びっくりしてしまった!!
藤
藤野燦太郎さん (9fhs4rfz)2025/2/8 17:46削除「ザ・ホエール」感想 藤野燦太郎
「白鯨」の書評エッセイがでてきたかと思えば、主人公は鯨のような巨漢であったりして、
誰が見ても関連づけたくなる作品でした。
舞台が暗く、汚いアパートの一室だけで、ここに5人の登場人物が入れ代わり立ち代わり入ってきて、ろくでもない過去を話す。月曜から金曜日までの話で、幸せな人は誰もおらず、皆何かを失った人ばかり。たいへん奥深く、考えさせられる作品でした。
1. テーマ 小説「白鯨」の枠組みが現代のアメリカのあるアパートの一室で展開されたものではないでしょうか。小説では「白鯨」とそれを追う「片足奪われた船長」とその仲間が描かれていますが、この映画では「鯨」に当たるチャーリー(275kg)と8歳で捨てられたと感じているエリーが主軸であるけれど、同じく捨てられたと思っている妻メアリー、またチャーリーが付き合っていて、その後死んだ男の妹リズ、お金を盗んで罰せられ、家族から追われた宣教師トーマス(直接チャーリーとは関係がない)。こんな喪失を抱えた4人がチャーリーを追っていくスタイルです。
この映画の奥底にあるテーマは「正直を貫くことの厳しさ」と思われ、なぜ捨てたのか、愛情がなかったのかを聞こうと迫ってくるエリーの「真実を追求する」姿勢をチャーリーは実はうれしく思っている。「正直に書くこと」をエッセイ講座で教えているし、「正直」に生きて男のもとへ走り、エリーやメアリーを捨てたこともあるくらいで、正直に生きることの厳しさを知っているからである。
チャーリーが娘エリーにエッセイを通じて、「正直」を貫いた不器用な父親をわかってほしかったのでしょう。「正直」を貫くことの厳しさ、降りかかってくる困難、他者を巻き込む様々な問題を乗り越えて、そして最後には少し気持ちを理解してもらえたように思います。
2. リズのチャーリーに対する感情はやはり「愛情」だと思います。兄を一時的に救ってくれた人であり、恩義を感じながら面倒を看ていますが、途中から愛情に変わっていったと思います。チャーリーが12万ドルも持っていたことが分かった時の怒りは、ビジネスとか友情とかでなく、愛情を裏切られた人の怒りではないでしょうか。
3. Daddy please! やはり、病気を治してもう一度人生をやり直してという気持ちが込められている。
4. 自由感想
チャーリーが立ち上がるシーンの後、その後白い光に包まれていったのは、チャーリーの心臓が止まって血圧が下がり、チャーリーの目には世界が白っぽく見えたということと、天国へ旅立ったということを映像であらわしたのかと思いました。
「白鯨」の書評エッセイがでてきたかと思えば、主人公は鯨のような巨漢であったりして、
誰が見ても関連づけたくなる作品でした。
舞台が暗く、汚いアパートの一室だけで、ここに5人の登場人物が入れ代わり立ち代わり入ってきて、ろくでもない過去を話す。月曜から金曜日までの話で、幸せな人は誰もおらず、皆何かを失った人ばかり。たいへん奥深く、考えさせられる作品でした。
1. テーマ 小説「白鯨」の枠組みが現代のアメリカのあるアパートの一室で展開されたものではないでしょうか。小説では「白鯨」とそれを追う「片足奪われた船長」とその仲間が描かれていますが、この映画では「鯨」に当たるチャーリー(275kg)と8歳で捨てられたと感じているエリーが主軸であるけれど、同じく捨てられたと思っている妻メアリー、またチャーリーが付き合っていて、その後死んだ男の妹リズ、お金を盗んで罰せられ、家族から追われた宣教師トーマス(直接チャーリーとは関係がない)。こんな喪失を抱えた4人がチャーリーを追っていくスタイルです。
この映画の奥底にあるテーマは「正直を貫くことの厳しさ」と思われ、なぜ捨てたのか、愛情がなかったのかを聞こうと迫ってくるエリーの「真実を追求する」姿勢をチャーリーは実はうれしく思っている。「正直に書くこと」をエッセイ講座で教えているし、「正直」に生きて男のもとへ走り、エリーやメアリーを捨てたこともあるくらいで、正直に生きることの厳しさを知っているからである。
チャーリーが娘エリーにエッセイを通じて、「正直」を貫いた不器用な父親をわかってほしかったのでしょう。「正直」を貫くことの厳しさ、降りかかってくる困難、他者を巻き込む様々な問題を乗り越えて、そして最後には少し気持ちを理解してもらえたように思います。
2. リズのチャーリーに対する感情はやはり「愛情」だと思います。兄を一時的に救ってくれた人であり、恩義を感じながら面倒を看ていますが、途中から愛情に変わっていったと思います。チャーリーが12万ドルも持っていたことが分かった時の怒りは、ビジネスとか友情とかでなく、愛情を裏切られた人の怒りではないでしょうか。
3. Daddy please! やはり、病気を治してもう一度人生をやり直してという気持ちが込められている。
4. 自由感想
チャーリーが立ち上がるシーンの後、その後白い光に包まれていったのは、チャーリーの心臓が止まって血圧が下がり、チャーリーの目には世界が白っぽく見えたということと、天国へ旅立ったということを映像であらわしたのかと思いました。
返信
返信8
管
管理者さん (8pa6wkw7)2024/11/18 14:24 (No.1328939)削除課題映画、第21回映画好きの集い(旧作)(2025年2月9日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
藤
藤野さん (8pa6wkw7)2025/1/10 08:39削除旧作課題映画 藤野
エディットピアフ愛の賛歌
前回はややマニアックな作品だったので、今回は伝記ものにしました。
シャンソン歌手エディットピアフの一生を扱っています。現在と過去が頻繁に交錯するため、ややわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
テーマ
1.デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
2.47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
3.この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
エディットピアフ愛の賛歌
前回はややマニアックな作品だったので、今回は伝記ものにしました。
シャンソン歌手エディットピアフの一生を扱っています。現在と過去が頻繁に交錯するため、ややわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
テーマ
1.デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
2.47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
3.この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
無
無敗の藤原さん (8pa6wkw7)2025/1/10 08:40削除破滅的な人生を送った彼女だからこそ表現に深みが生まれたのでしょうか。
もしそうだとしたら、虐げられた過去や別れの多い人生を少しでも肯定できる、だから彼女は最後に歌がないと行きていけないと言ったように思います。
【設問1】
デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
→
特定のシーンではないのですが、幼少期に周りが大人しかいなかったから愛を一方的に受け取るか、奪われるかしかなかった。
愛を与えるって経験をしてなかったから愛する対象が生まれたボクサーとの恋愛は燃えるようなものになったんだと思います。
そう考えると、ラストの一問一答で頻りに愛しなさいって答えてたことにつながるのかもしれない。
【設問2】
47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
→
元々はどれも知らない曲だったのですが、「水に流して」って最後にふたり組が持ってきた曲は歌詞を読む限りエディットピアフの人生を表していると思います。
酷い仕打ちを受けてきたけれども、今から始めると考えればいつでも前向きになれる、というようなメッセージを感じました。
【設問3】
この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
→
エディットピアフがよぼよぼのお婆さんになってるのを見てちょっとショックを受けたというか、スターとしての迫力が失われていることが悲しかったです。
ただ、若さには輝きがあるように、歳を取ることで発言の重さがあるように思います。死に瀕したエディットピアフの最後の言葉には説得力があるように思いました。
もしそうだとしたら、虐げられた過去や別れの多い人生を少しでも肯定できる、だから彼女は最後に歌がないと行きていけないと言ったように思います。
【設問1】
デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
→
特定のシーンではないのですが、幼少期に周りが大人しかいなかったから愛を一方的に受け取るか、奪われるかしかなかった。
愛を与えるって経験をしてなかったから愛する対象が生まれたボクサーとの恋愛は燃えるようなものになったんだと思います。
そう考えると、ラストの一問一答で頻りに愛しなさいって答えてたことにつながるのかもしれない。
【設問2】
47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
→
元々はどれも知らない曲だったのですが、「水に流して」って最後にふたり組が持ってきた曲は歌詞を読む限りエディットピアフの人生を表していると思います。
酷い仕打ちを受けてきたけれども、今から始めると考えればいつでも前向きになれる、というようなメッセージを感じました。
【設問3】
この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
→
エディットピアフがよぼよぼのお婆さんになってるのを見てちょっとショックを受けたというか、スターとしての迫力が失われていることが悲しかったです。
ただ、若さには輝きがあるように、歳を取ることで発言の重さがあるように思います。死に瀕したエディットピアフの最後の言葉には説得力があるように思いました。
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2025/1/10 11:39削除『エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜』
テーマ
1.デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
⇒幼くして母が娘を置いて出ていき、大道芸人である父に引き取られることになり、その父も手に余り、自分の母親が営む売春宿にエディットを預ける事になる。
やがて父親がエディットを引き取りに来るが、せっかく仲良くしてくれた女郎からも引き離されることになるシーン。
成長したエディットの下に娘を捨てて出て行った母が金の無心に現れるシーン。
2.47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
⇒一つ一つの曲名こそ知らないが、彼女の独特の声質、声量はさすが持って生まれた才能の塊を感じた。
路上で歌っているエディットをクラブの支配人がスカウトするわけだが、されるべくしてされたのだと感じた。
表題の通り、愛の讃歌は今回初めてエディット・ピアフ版で聞いたが、さすがシャンソン歌手であると感銘を受けた。
改めてエディット・ピアフの歌声をCDなりで聞いたみたいと思った。
47歳という若さでこの世を去ったという事だが、画面上では70歳の老婆であるとずっと思っていた。
3.この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
⇒エディット・ピアフの寂しかった老後を彼女の報われなかった人生を象徴する様に、敢えてみすぼらしく撮ったのではないでしょうか?
今回エディット・ピアフの生涯を映画化した本作を初めて観た。正直言うとエディット・ピアフという名前を初めて知った。愛の讃歌は越路吹雪が歌い、むしろ日本語の歌詞は口を突いて出る事はあるが、この原曲を聞くことは無かった。
シャンソン=越路吹雪くらいに思っていたわけだが、本家のエディット・ピアフの歌声を聞いてみて、エディットの方がドスが利いていると感じた。
またエディット・ピアフからシャンソンを取ってしまうと本当に何も残らないのかもしれないとも感じた。これは悪口ではなく、シャンソンの為だけに生まれて来た天才であるという証である。
テーマ
1.デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつか挙げてください。
⇒幼くして母が娘を置いて出ていき、大道芸人である父に引き取られることになり、その父も手に余り、自分の母親が営む売春宿にエディットを預ける事になる。
やがて父親がエディットを引き取りに来るが、せっかく仲良くしてくれた女郎からも引き離されることになるシーン。
成長したエディットの下に娘を捨てて出て行った母が金の無心に現れるシーン。
2.47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
⇒一つ一つの曲名こそ知らないが、彼女の独特の声質、声量はさすが持って生まれた才能の塊を感じた。
路上で歌っているエディットをクラブの支配人がスカウトするわけだが、されるべくしてされたのだと感じた。
表題の通り、愛の讃歌は今回初めてエディット・ピアフ版で聞いたが、さすがシャンソン歌手であると感銘を受けた。
改めてエディット・ピアフの歌声をCDなりで聞いたみたいと思った。
47歳という若さでこの世を去ったという事だが、画面上では70歳の老婆であるとずっと思っていた。
3.この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
⇒エディット・ピアフの寂しかった老後を彼女の報われなかった人生を象徴する様に、敢えてみすぼらしく撮ったのではないでしょうか?
今回エディット・ピアフの生涯を映画化した本作を初めて観た。正直言うとエディット・ピアフという名前を初めて知った。愛の讃歌は越路吹雪が歌い、むしろ日本語の歌詞は口を突いて出る事はあるが、この原曲を聞くことは無かった。
シャンソン=越路吹雪くらいに思っていたわけだが、本家のエディット・ピアフの歌声を聞いてみて、エディットの方がドスが利いていると感じた。
またエディット・ピアフからシャンソンを取ってしまうと本当に何も残らないのかもしれないとも感じた。これは悪口ではなく、シャンソンの為だけに生まれて来た天才であるという証である。
藤
藤野燦太郎さん (8j4tkzsk)2025/2/3 23:24削除旧作課題映画 藤野
エディットピアフ愛の賛歌
前回はややマニアックな作品だったので、今回は伝記ものにしました。
世界的シャンソン歌手の一生を扱っていますが、現在と過去が頻繁に交錯するため、ややわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
テーマ
1. デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、最も印象的なシーンは何処でしょうか。
自分のわがままから飛行機で戻るようにセルダンに電話し、飛行機が墜落したという連絡を受けた時。自分が殺したかのように大混乱するピアフは強烈な印象でした。
2. 47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
やはり、「愛の賛歌」です。セルダンが墜落死したのに、その日のコンサートでこれを歌っている。歌詞の日本語訳では、
「あなたが望めば、財宝だって盗みに行く」とか、「国を裏切り、友を裏切る」とか、「あなたが死んでしまっても、つらくない。私もついていく、永遠の命を得てーーー」などと危険な歌詞であることがわかります。しかしこれがピアフの生き方なんだろうと思います。
3. この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
ピアフは娼婦街、日本でいえば遊郭で育った人で、父親出征中で本来守るべき立場にあった母親にまで捨てられた人でした。現在と過去を行ったり来たりする構成で、現在の薬物依存でボロボロになった身体や人の都合を全く考えないわがままは、生きていくのがやっとの貧乏生活や母親に捨てられ、愛に恵まれなかった少女時代を描くことによって初めて理解されると思います。また、このような娼婦街や遊郭で育って大成功した歌手は世界にいないようです。ピアフを描くにはこの人生に大きな影を落とした、娼婦街での少女時代を描かなければならないように思います。
このような起伏が激しく暗い構成でないとピアフという人は描けないということなのでしょう。
参考 ピアフの死因は肝臓がんです。ピアフは薬物依存症であり、モルヒネを頻繁に注射していました。当時はB型やC型肝炎ウイルスが注射器の使いまわしで感染することが知られていませんでした。日本ではB型肝炎だけでも120万人いると言われ、かなりの部分が学校の予防注射で感染しています。日本は1988年になってようやく注射器の使いまわしを禁じ、それ以前に感染した人に対して国家が賠償をしています。
ここからは私の想像ですが、ピアフはB型あるいはC型肝炎に感染し、最後に肝臓癌になったという、典型的なコースをたどったのではないでしょうか。
エディットピアフ愛の賛歌
前回はややマニアックな作品だったので、今回は伝記ものにしました。
世界的シャンソン歌手の一生を扱っていますが、現在と過去が頻繁に交錯するため、ややわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
テーマ
1. デビューしてからもずっと愛に飢えた人生でしたが、最も印象的なシーンは何処でしょうか。
自分のわがままから飛行機で戻るようにセルダンに電話し、飛行機が墜落したという連絡を受けた時。自分が殺したかのように大混乱するピアフは強烈な印象でした。
2. 47年という短い人生でしたが、彼女の歌った曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか。
やはり、「愛の賛歌」です。セルダンが墜落死したのに、その日のコンサートでこれを歌っている。歌詞の日本語訳では、
「あなたが望めば、財宝だって盗みに行く」とか、「国を裏切り、友を裏切る」とか、「あなたが死んでしまっても、つらくない。私もついていく、永遠の命を得てーーー」などと危険な歌詞であることがわかります。しかしこれがピアフの生き方なんだろうと思います。
3. この種の映画では、感動的なラストシーンを作ることが多いですが、あえて腰がひどく曲がって老婆になった彼女に、インタビューまでしています。監督の狙いは何処にあるのでしょうか。
ピアフは娼婦街、日本でいえば遊郭で育った人で、父親出征中で本来守るべき立場にあった母親にまで捨てられた人でした。現在と過去を行ったり来たりする構成で、現在の薬物依存でボロボロになった身体や人の都合を全く考えないわがままは、生きていくのがやっとの貧乏生活や母親に捨てられ、愛に恵まれなかった少女時代を描くことによって初めて理解されると思います。また、このような娼婦街や遊郭で育って大成功した歌手は世界にいないようです。ピアフを描くにはこの人生に大きな影を落とした、娼婦街での少女時代を描かなければならないように思います。
このような起伏が激しく暗い構成でないとピアフという人は描けないということなのでしょう。
参考 ピアフの死因は肝臓がんです。ピアフは薬物依存症であり、モルヒネを頻繁に注射していました。当時はB型やC型肝炎ウイルスが注射器の使いまわしで感染することが知られていませんでした。日本ではB型肝炎だけでも120万人いると言われ、かなりの部分が学校の予防注射で感染しています。日本は1988年になってようやく注射器の使いまわしを禁じ、それ以前に感染した人に対して国家が賠償をしています。
ここからは私の想像ですが、ピアフはB型あるいはC型肝炎に感染し、最後に肝臓癌になったという、典型的なコースをたどったのではないでしょうか。
清
清水伸子さん (8p590r59)2025/2/5 17:25削除課題1.デビューしてからもずっと会いに飢えた人生でしたが、そんな性格になった印象的なシーンをいくつかあげてください
可愛がり愛情を注いでくれていた娼婦たちから引き離される場面.次にようやく居場所を見つけたサーカスも去らなければならなくなった場面、母親からもお金をせびられる場面など
課題2.彼女の歌った歌の中で彼女の人生を最も表現した曲はなんだと思いますか?
「愛の讃歌」と共に映画のラストの歌「いえ後悔しないわ」
課題3.この映画であえて腰の曲がった老婆になった彼女にインタビューしている監督の狙いはどこにあるのでしょうか?
彼女のありのままの姿を伝え、ラストのオランピア劇場で歌う姿とオーバーラッピングさせる効果を狙っていると思いました.
可愛がり愛情を注いでくれていた娼婦たちから引き離される場面.次にようやく居場所を見つけたサーカスも去らなければならなくなった場面、母親からもお金をせびられる場面など
課題2.彼女の歌った歌の中で彼女の人生を最も表現した曲はなんだと思いますか?
「愛の讃歌」と共に映画のラストの歌「いえ後悔しないわ」
課題3.この映画であえて腰の曲がった老婆になった彼女にインタビューしている監督の狙いはどこにあるのでしょうか?
彼女のありのままの姿を伝え、ラストのオランピア劇場で歌う姿とオーバーラッピングさせる効果を狙っていると思いました.
上
上終結城さん (8g07wmfj)2025/2/5 20:59削除1.はじめに
本作は公開当時映画館で観たが、ほとんど忘れている。記憶に残りにくかった理由のひとつは、時間が目まぐるしく前後する編集方法にあったかもしれない。しかしピアフが恋人の死を聞かされるシーンはよく覚えている。今回再度観なおし、あらためて作品の良さを味わうことができた。
2.課題について
【課題1】愛に飢えた性格になった印象的なシーンは?
【回答1】
祖母の売春宿に引き取られた幼いピアフを、わが子のように可愛がってくれた娼婦ティティーヌとの別れのシーン(父親とともにサーカス巡業に連れていかれる)。ピアフは母親からはろくに愛情を受けておらず、むしろ確執がある。一方、父親とは親子の愛情があったのだろう。死の迫った病床でピアフは「パパのために祈りたい」と言っている。
【課題2】彼女の曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか?
【回答2】
とくに印象的なのはつぎの三曲。
①「バラ色の人生」:大女優マリーネ・デートリッヒがピアフのテーブルに来て、ピアフの歌を称賛する場面。ピアフの最も輝かしい瞬間だろう。
②「愛の讃歌」:恋人セルダンが飛行機事故で死んだとの知らせを受ける場面。ワンカットの長回しで、知らせを聞き泣き叫ぶピアフが、そのまま悲嘆にくれた状態で、いつの間にか観客が待つ舞台に立っている。ここの演出は素晴らしい。ここで唄うのが「愛の讃歌」。
③「水に流して」:最後の舞台でこの歌を唄う。歌詞は自分の人生を振り返り、すべてご破算にして前を向く、というもの。
【課題3】老婆になった彼女まで描く監督の狙いは?
【回答3】
47年の短いながら濃縮したピアフの人生。その栄光も悲惨も、すべてを肯定するためだろう。
3.その他
私は2023年2月にジュディ・ガーランドを描いた伝記映画『ジュディ 虹の彼方に』(2019)をとりあげた。この映画では時代設定を彼女の晩年(といっても47歳)に絞り、回想シーンは少なめだった。そして映画は、イギリス公演最後の舞台でジュディが、ともに合唱し拍手する観客に投げキッスをする場面で終わる。その6ヶ月後の悲劇的な死は字幕で表示されるだけで、本編では描かれない。形としてはハッピーエンドに見える。
一方、『エディット・ピアフ ~愛の讃歌~』では、衰弱し、醜く老いた彼女もリアルに描いている。終わり方をあくまで明るくする米映画と、終わり方に人生の苦さをにじませる仏、英映画との違いだろうか。
本作は公開当時映画館で観たが、ほとんど忘れている。記憶に残りにくかった理由のひとつは、時間が目まぐるしく前後する編集方法にあったかもしれない。しかしピアフが恋人の死を聞かされるシーンはよく覚えている。今回再度観なおし、あらためて作品の良さを味わうことができた。
2.課題について
【課題1】愛に飢えた性格になった印象的なシーンは?
【回答1】
祖母の売春宿に引き取られた幼いピアフを、わが子のように可愛がってくれた娼婦ティティーヌとの別れのシーン(父親とともにサーカス巡業に連れていかれる)。ピアフは母親からはろくに愛情を受けておらず、むしろ確執がある。一方、父親とは親子の愛情があったのだろう。死の迫った病床でピアフは「パパのために祈りたい」と言っている。
【課題2】彼女の曲の中で、彼女の人生を最も表現した曲は何だと思いますか?
【回答2】
とくに印象的なのはつぎの三曲。
①「バラ色の人生」:大女優マリーネ・デートリッヒがピアフのテーブルに来て、ピアフの歌を称賛する場面。ピアフの最も輝かしい瞬間だろう。
②「愛の讃歌」:恋人セルダンが飛行機事故で死んだとの知らせを受ける場面。ワンカットの長回しで、知らせを聞き泣き叫ぶピアフが、そのまま悲嘆にくれた状態で、いつの間にか観客が待つ舞台に立っている。ここの演出は素晴らしい。ここで唄うのが「愛の讃歌」。
③「水に流して」:最後の舞台でこの歌を唄う。歌詞は自分の人生を振り返り、すべてご破算にして前を向く、というもの。
【課題3】老婆になった彼女まで描く監督の狙いは?
【回答3】
47年の短いながら濃縮したピアフの人生。その栄光も悲惨も、すべてを肯定するためだろう。
3.その他
私は2023年2月にジュディ・ガーランドを描いた伝記映画『ジュディ 虹の彼方に』(2019)をとりあげた。この映画では時代設定を彼女の晩年(といっても47歳)に絞り、回想シーンは少なめだった。そして映画は、イギリス公演最後の舞台でジュディが、ともに合唱し拍手する観客に投げキッスをする場面で終わる。その6ヶ月後の悲劇的な死は字幕で表示されるだけで、本編では描かれない。形としてはハッピーエンドに見える。
一方、『エディット・ピアフ ~愛の讃歌~』では、衰弱し、醜く老いた彼女もリアルに描いている。終わり方をあくまで明るくする米映画と、終わり方に人生の苦さをにじませる仏、英映画との違いだろうか。
池
池内健さん (9fbmysza)2025/2/6 09:24削除1.愛に飢えた人生
ピアフは大人の都合でたらい回しにされる幼年時代を過ごした。娼館でもサーカスでも、なじんできて愛着が湧いた頃に引き離される。大道芸人になった父が最終的に引き取るが、これも子供づれの方が目を引いて客が集まるという打算に過ぎない。十分に愛されたことがなければ愛することはできない。大人になってからの男性遍歴も、相手に求めるばかりだった。
2.彼女の人生を最も表現した曲
ドスの利いた歌声は、歌手だった母から受け継いだ天性のものである以上に、平坦ではなかった人生が作り上げたもの。門付けから発展した津軽三味線の地吹雪のような音色を想起させる。父に何か芸をやれと言われて歌う「ラマルセイエーズ」ですら異様な迫力を感じた(ピアフの歌声ではないかもしれないが)。歌には生き方がにじみ出るから、何を歌ってもピアフならではだったと思う。
3.老婆になったラスト
よぼよぼの老人にしかみえない彼女が47歳というのはショックだが、死ぬまで歌に固執した人生を表現するには効果的だったのではないか。
ピアフは大人の都合でたらい回しにされる幼年時代を過ごした。娼館でもサーカスでも、なじんできて愛着が湧いた頃に引き離される。大道芸人になった父が最終的に引き取るが、これも子供づれの方が目を引いて客が集まるという打算に過ぎない。十分に愛されたことがなければ愛することはできない。大人になってからの男性遍歴も、相手に求めるばかりだった。
2.彼女の人生を最も表現した曲
ドスの利いた歌声は、歌手だった母から受け継いだ天性のものである以上に、平坦ではなかった人生が作り上げたもの。門付けから発展した津軽三味線の地吹雪のような音色を想起させる。父に何か芸をやれと言われて歌う「ラマルセイエーズ」ですら異様な迫力を感じた(ピアフの歌声ではないかもしれないが)。歌には生き方がにじみ出るから、何を歌ってもピアフならではだったと思う。
3.老婆になったラスト
よぼよぼの老人にしかみえない彼女が47歳というのはショックだが、死ぬまで歌に固執した人生を表現するには効果的だったのではないか。
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2025/2/6 16:04削除「エディット・ピアフ 愛の讃歌」を観て
1. ずっと愛に飢えた人生、そんな印象的シーンは?
やはり子供時代の路上で歌うシーンだろう。まず親の愛を得るために、認めてもらうために、彼女は路上で歌うしかなかった。皮肉にもその才能が彼女の人生を助けることになるのだが。実際には地下鉄の通路で歌うことも多かったらしい。マイクも無く、彼女の声量や聴いてもらうための技量はここで鍛えられたのだろう。
2. 47年の彼女の人生を最も表した曲は?
この映画のフランスでの原題は「La Mome」で子どもとかガキとかの意味。まさに子供のような、ストリートチルドレンのような、そのままの人生だったのだろう。
そして日本題は「エディット・ピアフ愛の讃歌」。やはり「愛の讃歌」が日本では一番有名であり、誰もがピンとくるからだろう。英題は「La Vie En Rose」でフランス語だが日本語にすると「バラ色の人生」。これも彼女の大ヒット曲だ。この2曲は彼女自身の作詞である。
だが、彼女が愛する恋人のボクサー、マルセル・セルダンを失い、病気や薬物によって健康も失って悲嘆にくれた後に再起して歌った「水に流して」は彼女の作詞ではないが、映画内でも彼女が言っているように一番彼女の人生を表しているように思う。
3. 感動的なラストシーンでなく、老婆のような彼女にインタビューした監督の狙いは?
作り物でなく、嘘偽りのないドキュメンタリー的な味わいの映画にしたかったからでは。
それにしても、マリオン・コティヤールの演技は凄かった。腰は曲がって髪がうすくよぼよぼの本当の老婆のように見える。実際に47歳のエディットもこんな感じだったのだろうと推察できる。シャンソンを歌うために生まれ、死んでいった歌手なのだろう。
1. ずっと愛に飢えた人生、そんな印象的シーンは?
やはり子供時代の路上で歌うシーンだろう。まず親の愛を得るために、認めてもらうために、彼女は路上で歌うしかなかった。皮肉にもその才能が彼女の人生を助けることになるのだが。実際には地下鉄の通路で歌うことも多かったらしい。マイクも無く、彼女の声量や聴いてもらうための技量はここで鍛えられたのだろう。
2. 47年の彼女の人生を最も表した曲は?
この映画のフランスでの原題は「La Mome」で子どもとかガキとかの意味。まさに子供のような、ストリートチルドレンのような、そのままの人生だったのだろう。
そして日本題は「エディット・ピアフ愛の讃歌」。やはり「愛の讃歌」が日本では一番有名であり、誰もがピンとくるからだろう。英題は「La Vie En Rose」でフランス語だが日本語にすると「バラ色の人生」。これも彼女の大ヒット曲だ。この2曲は彼女自身の作詞である。
だが、彼女が愛する恋人のボクサー、マルセル・セルダンを失い、病気や薬物によって健康も失って悲嘆にくれた後に再起して歌った「水に流して」は彼女の作詞ではないが、映画内でも彼女が言っているように一番彼女の人生を表しているように思う。
3. 感動的なラストシーンでなく、老婆のような彼女にインタビューした監督の狙いは?
作り物でなく、嘘偽りのないドキュメンタリー的な味わいの映画にしたかったからでは。
それにしても、マリオン・コティヤールの演技は凄かった。腰は曲がって髪がうすくよぼよぼの本当の老婆のように見える。実際に47歳のエディットもこんな感じだったのだろうと推察できる。シャンソンを歌うために生まれ、死んでいった歌手なのだろう。
返信
返信8
管
管理者さん (8pa6wkw7)2024/11/18 14:26 (No.1328943)削除第21回文横映画好きの集い(自由映画)(2025年2月9日)について、ご自由に感想をお書込みください!
返信
返信0
管
管理者さん (8pa6wkw7)2024/8/21 13:43 (No.1245448)削除課題映画、第20回映画好きの集い(新作)(2024年11月17日)について、テーマに続き感想を自由にお書込みください!
池
池内健さん (98cgg0kf)2024/8/27 06:38削除課題映画 新作『TAR/ター』(2022年、アメリカ)
ベルリンフィルのカリスマ的女性指揮者リディア・ターの物語。主役のケイト・ブランシェットが好きなこと、音楽を扱った映画に名作が多いことから課題に選びました。
ターは架空の役柄ですが、脚本には実際に音楽界で起きたスキャンダルが盛り込まれています。美しい音楽をめぐるどろどろした人間模様も興味深いところです。ブランシェットはこの作品でベネチア国際映画祭の女優賞を得ました。
みなさんにお聞きしたい項目は以下の通りです。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
【課題3】
ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
ベルリンフィルのカリスマ的女性指揮者リディア・ターの物語。主役のケイト・ブランシェットが好きなこと、音楽を扱った映画に名作が多いことから課題に選びました。
ターは架空の役柄ですが、脚本には実際に音楽界で起きたスキャンダルが盛り込まれています。美しい音楽をめぐるどろどろした人間模様も興味深いところです。ブランシェットはこの作品でベネチア国際映画祭の女優賞を得ました。
みなさんにお聞きしたい項目は以下の通りです。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
【課題3】
ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
無
無敗の藤原さん (95c8u6fd)2024/9/8 21:19削除課題映画「TAR/ター」について。
最初見たときは、まーなんて難解な映画だろうと思いました。
2回見ることが前提、みたいな映画なのかもしれません。
後の展開の布石は置かれているものの、1回目の視聴ではその情報がうまく掴めませんでした。でも2回目見ると、ここでこれ言ってたんだな〜って納得するシーンが多かったです。
2回見てもわからないシーンがまだあるので、みなさんの感想楽しみです。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
→
この映画の前半部分を見ている時は正直理解が全然できなくて、退屈だなと感じていました。
その印象が180度変わった瞬間がありまして、ターが家でアコーディオンで演奏しながら叫ぶように歌うシーンです。
亡くなった隣人の娘さんたちが来て、ターの音楽を騒音と言ったところですね。
ターはそれまでなんとか狂わないように耐えてきた(問題のある行動は多かったとは言え)と思うんですけど、ここでダムが決壊するような開放感があって印象に残ってます。
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
→
教え子の自殺が一番考えさせられました。我々は主人公のターをずっと追ってきてわけですから感情移入しちゃって、どうすればよかったんだって気持ちになりました。
相手の行動をコントロールすることは基本できないわけで、その人が生きていれば自分は被害者でその人が死ぬことによって自分が加害者になるって状況はやるせないなと。
【課題3】
ラストシーンは、東南アジアと思われる国のコスプレイヤーが集まるコンサート。このラストをどう感じたか(どのように解釈したか)
→
ターが音楽を純粋に楽しむ場所から再スタートしたように感じました。
その前のシーンで白黒のビデオを見て、音楽は理論じゃないという言葉に涙してたりしましたから。
コスプレしながら音楽を聞くなんて学園祭みたいな感じですし、楽しさに立ち返るって流れはおかしくないと思います。
ただ一方で、私が拾いきれてない意図がありそうです。
ラストシーンは明らかにこれまでとは違う描写、絵的にもガラッと雰囲気が変わって、何の説明もない。そんなシーンをラストのラストに持ってきてるって、なんか深い意図がありそうです。
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
→
「アマデウス」という映画が好きです。
負けた人間の苦悩を描いていてとても心に残る作品です。
最初見たときは、まーなんて難解な映画だろうと思いました。
2回見ることが前提、みたいな映画なのかもしれません。
後の展開の布石は置かれているものの、1回目の視聴ではその情報がうまく掴めませんでした。でも2回目見ると、ここでこれ言ってたんだな〜って納得するシーンが多かったです。
2回見てもわからないシーンがまだあるので、みなさんの感想楽しみです。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
→
この映画の前半部分を見ている時は正直理解が全然できなくて、退屈だなと感じていました。
その印象が180度変わった瞬間がありまして、ターが家でアコーディオンで演奏しながら叫ぶように歌うシーンです。
亡くなった隣人の娘さんたちが来て、ターの音楽を騒音と言ったところですね。
ターはそれまでなんとか狂わないように耐えてきた(問題のある行動は多かったとは言え)と思うんですけど、ここでダムが決壊するような開放感があって印象に残ってます。
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
→
教え子の自殺が一番考えさせられました。我々は主人公のターをずっと追ってきてわけですから感情移入しちゃって、どうすればよかったんだって気持ちになりました。
相手の行動をコントロールすることは基本できないわけで、その人が生きていれば自分は被害者でその人が死ぬことによって自分が加害者になるって状況はやるせないなと。
【課題3】
ラストシーンは、東南アジアと思われる国のコスプレイヤーが集まるコンサート。このラストをどう感じたか(どのように解釈したか)
→
ターが音楽を純粋に楽しむ場所から再スタートしたように感じました。
その前のシーンで白黒のビデオを見て、音楽は理論じゃないという言葉に涙してたりしましたから。
コスプレしながら音楽を聞くなんて学園祭みたいな感じですし、楽しさに立ち返るって流れはおかしくないと思います。
ただ一方で、私が拾いきれてない意図がありそうです。
ラストシーンは明らかにこれまでとは違う描写、絵的にもガラッと雰囲気が変わって、何の説明もない。そんなシーンをラストのラストに持ってきてるって、なんか深い意図がありそうです。
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
→
「アマデウス」という映画が好きです。
負けた人間の苦悩を描いていてとても心に残る作品です。
清
清水伸子さん (8p590r59)2024/9/10 18:05削除前半の対談と対話部分がとても長く、内容も専門的で難しく、またクリスタはなぜ自殺したのか、フランチェスカが頻繁にメールしていたのは何のやりとりだったのか、メトロノームは何なのか?オルガが帰って行った廃墟のような場所は何なのか?マッサージ店が出てくる意味は?など私には謎の多い映画でした.
課題1
最も印象的だったシーンはターがトイレに隠れ、鬼気迫る姿で指揮台に立とうとするシーンです.
課題2
一番興味を引かれたテーマは、音楽という一見美しい芸術の世界に渦巻く陰謀や裏切りが、簡単に才能を押し潰していまう怖さでしょうか
課題3
唐突なラストでただただ驚きました、ここにしかターの居場所はなくても音楽に携わろうとする姿を描いているのかとも思いましたが、よく分かりません、
課題4
おすすめの音楽映画としては「はじまりのうたカッコ」や「ボヘミアンラブソデイー」「コーダあいのうた」「セッション」などでしょうか
最後に、ケイト ブランシェットの演技は素晴らしいと思いました.指揮者として作曲家として良い音楽を創り上げようとする姿に演技を超えた本物を感じました.マエストロとしてオーケストラの頂点に立ち指揮をする時の迫力、一人の時、舞台に立つ前などのピリピリした繊細さなどが際立ちました.
私が謎に思った点など皆様の感想やご意見を伺うのが楽しみです.
課題1
最も印象的だったシーンはターがトイレに隠れ、鬼気迫る姿で指揮台に立とうとするシーンです.
課題2
一番興味を引かれたテーマは、音楽という一見美しい芸術の世界に渦巻く陰謀や裏切りが、簡単に才能を押し潰していまう怖さでしょうか
課題3
唐突なラストでただただ驚きました、ここにしかターの居場所はなくても音楽に携わろうとする姿を描いているのかとも思いましたが、よく分かりません、
課題4
おすすめの音楽映画としては「はじまりのうたカッコ」や「ボヘミアンラブソデイー」「コーダあいのうた」「セッション」などでしょうか
最後に、ケイト ブランシェットの演技は素晴らしいと思いました.指揮者として作曲家として良い音楽を創り上げようとする姿に演技を超えた本物を感じました.マエストロとしてオーケストラの頂点に立ち指揮をする時の迫力、一人の時、舞台に立つ前などのピリピリした繊細さなどが際立ちました.
私が謎に思った点など皆様の感想やご意見を伺うのが楽しみです.
藤
藤堂勝汰さん (8pa6wkw7)2024/11/5 10:39削除『TAR/ター』を観た。158分と長尺な作品とういう事もあり、また前半の部分が今一つ内容が不明で、退屈しかかり一気見できない状態があった。
改めて、時間と態勢を整えて、TAR/ターと向き合い、見切ることができた。
見終えてみると、中盤からTARという主人公の人生が少しずつ崩壊し始め、没落していく様を見るにつけ、どこまで堕ちていくのだろうかという興味に変わっていった。
自身に満ち溢れ、その発言はビッグマウスとも取れ、人を見下す態度が鼻に付くと思っていた冒頭の部分に自分自身が辟易して途中で観ている事が嫌になったのだなと見終わってようやく理解できた。
とかくこういった人間は傲慢の度合いが一旦頂点に達しない限り、気付けるチャンスはやって来ないというのが定番であり、まさに「平家物語」の一節「おごれる人も久しからず」を絵に描いたストーリー展開となっている。
傲慢な態度と言うのは最初自信家の表れと評されることも度々あるが、その一歩先には時に世間のバッシングが待ち伏せており、そのバッシング迄至らないと、気付けない。
政治家も芸能人も著名人も、この手の「煽て(おだて)」に乗り、世の中の大半が自分の味方であると勘違いし、その行く先でつっかえ棒を外され、手の平を返したように称賛から誹謗中傷へと態度や発言が一変する。
こんな光景は日常茶飯事となっている。見ている側は、大半がこの傲慢から没落になる光景を、バッシングされる姿を面白おかしく眺めているのである。
このTARでは、主人公のリディアは様々な身近の者に対して非情なまでの仕打ちを行う。
①気に食わない学生を吊し上げて退席させる。
②長年仕えて来た副指揮者を非情に切り捨てる
③裏切ったクリスタが音楽業界で働けないように、非難するメールを各所に送る。
④秘書のフランチェスカを副指揮者に抜擢するように言いながら、他の男性に地位を与える。
⑤これらの事がばれそうになると、隠ぺい工作を図る。開き直る。
一つの綻びが他の綻びを作り、やがてTARの人間性へのバッシングに発展していく。やがて彼女はその首席指揮者という地位を失い、一線の音楽業界に居られなくなっていく。
落ちぶれた彼女に手を差し伸べてくれたのは、フィリピンで指揮の仕事だった。行きついた場所は世界的なベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ほどちやほやされる場所ではなかったが、音楽好きな彼女が肩肘張らなくてよい一番に落ち着ける場所であったのかもしれない。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
(藤堂)取り乱したリディアがコンサートの指揮から外され、当日に満員の観客の前で代役の指揮者を指揮台から引きずり降ろすシーン。警備員に取り押さえられ、外に連れ出されていく。
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
(藤堂)典型的なセクハラ・パワハラの数々。自分の性欲のままに、自分の部下や弟子に対して権力やえさををちらつかせて、思いのままにしようとする。
それが思うように捗らないと、力づくで排除しようとする様。
【課題3】
ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
(藤堂)再起の為の最後のチャンス。彼女がフィリピンで仮装したオタクたちが聴衆のゲーム音楽のコンサートでも指揮棒を振るってみたいと思ったのは、彼女の音楽に対する純粋な欲望である。
もしも彼女が自分のプライドを守っていたら、まだ傲慢な一面が残っていたら、彼女はこの仕事を受けなかったと思う。
リディアには音楽の才能があり、その才能を開花させる手始めの仕事となって行くと思わせた。
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
(藤堂)自分が今まで見た映画の中で、一番に感銘を受けた音楽映画は、「ボヘミアン・ラプソディ」ですね。
当時、話題になり映画を観た後、CDを購入し、映画DVDも購入しました。
フレディ・マーキュリーは今回の映画「TAR/ター」のリディア・ターとダブる。
彼もまた同性愛者で、NO1ミュージッシャンに駆け上がるが、一人でもやっていけると勘違いをして、周りのバンドメンバーを切り捨てる。
だがエイズが発覚し、はじめて自分一人では何にもできないという事に気付き、仲間に詫びを入れ、再生していく。
ライブエイドでの彼の勇姿は観る人々の溜飲を下げる 。
改めて、時間と態勢を整えて、TAR/ターと向き合い、見切ることができた。
見終えてみると、中盤からTARという主人公の人生が少しずつ崩壊し始め、没落していく様を見るにつけ、どこまで堕ちていくのだろうかという興味に変わっていった。
自身に満ち溢れ、その発言はビッグマウスとも取れ、人を見下す態度が鼻に付くと思っていた冒頭の部分に自分自身が辟易して途中で観ている事が嫌になったのだなと見終わってようやく理解できた。
とかくこういった人間は傲慢の度合いが一旦頂点に達しない限り、気付けるチャンスはやって来ないというのが定番であり、まさに「平家物語」の一節「おごれる人も久しからず」を絵に描いたストーリー展開となっている。
傲慢な態度と言うのは最初自信家の表れと評されることも度々あるが、その一歩先には時に世間のバッシングが待ち伏せており、そのバッシング迄至らないと、気付けない。
政治家も芸能人も著名人も、この手の「煽て(おだて)」に乗り、世の中の大半が自分の味方であると勘違いし、その行く先でつっかえ棒を外され、手の平を返したように称賛から誹謗中傷へと態度や発言が一変する。
こんな光景は日常茶飯事となっている。見ている側は、大半がこの傲慢から没落になる光景を、バッシングされる姿を面白おかしく眺めているのである。
このTARでは、主人公のリディアは様々な身近の者に対して非情なまでの仕打ちを行う。
①気に食わない学生を吊し上げて退席させる。
②長年仕えて来た副指揮者を非情に切り捨てる
③裏切ったクリスタが音楽業界で働けないように、非難するメールを各所に送る。
④秘書のフランチェスカを副指揮者に抜擢するように言いながら、他の男性に地位を与える。
⑤これらの事がばれそうになると、隠ぺい工作を図る。開き直る。
一つの綻びが他の綻びを作り、やがてTARの人間性へのバッシングに発展していく。やがて彼女はその首席指揮者という地位を失い、一線の音楽業界に居られなくなっていく。
落ちぶれた彼女に手を差し伸べてくれたのは、フィリピンで指揮の仕事だった。行きついた場所は世界的なベルリン・フィルハーモニー管弦楽団ほどちやほやされる場所ではなかったが、音楽好きな彼女が肩肘張らなくてよい一番に落ち着ける場所であったのかもしれない。
【課題1】
もっとも印象的だったシーンとその理由は?
(藤堂)取り乱したリディアがコンサートの指揮から外され、当日に満員の観客の前で代役の指揮者を指揮台から引きずり降ろすシーン。警備員に取り押さえられ、外に連れ出されていく。
【課題2】
芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。この映画には多くのテーマが盛り込まれている。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
(藤堂)典型的なセクハラ・パワハラの数々。自分の性欲のままに、自分の部下や弟子に対して権力やえさををちらつかせて、思いのままにしようとする。
それが思うように捗らないと、力づくで排除しようとする様。
【課題3】
ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
(藤堂)再起の為の最後のチャンス。彼女がフィリピンで仮装したオタクたちが聴衆のゲーム音楽のコンサートでも指揮棒を振るってみたいと思ったのは、彼女の音楽に対する純粋な欲望である。
もしも彼女が自分のプライドを守っていたら、まだ傲慢な一面が残っていたら、彼女はこの仕事を受けなかったと思う。
リディアには音楽の才能があり、その才能を開花させる手始めの仕事となって行くと思わせた。
【課題4】
お薦めの音楽映画があれば
(藤堂)自分が今まで見た映画の中で、一番に感銘を受けた音楽映画は、「ボヘミアン・ラプソディ」ですね。
当時、話題になり映画を観た後、CDを購入し、映画DVDも購入しました。
フレディ・マーキュリーは今回の映画「TAR/ター」のリディア・ターとダブる。
彼もまた同性愛者で、NO1ミュージッシャンに駆け上がるが、一人でもやっていけると勘違いをして、周りのバンドメンバーを切り捨てる。
だがエイズが発覚し、はじめて自分一人では何にもできないという事に気付き、仲間に詫びを入れ、再生していく。
ライブエイドでの彼の勇姿は観る人々の溜飲を下げる 。
山
山口愛理さん (9bsqpmjl)2024/11/7 15:13削除TARを観て
1. 最も印象的だったシーンとその理由
映画のはじめのころは少し退屈で、中盤に行くにしたがって面白くなっていった。それにしても難解な映画だ。
最も印象的だったのはベルリン・フィルで指揮者の座を追い出され、現指揮者の男性に暴力を振るおうとするところ。彼女の激昂ぶりが凄まじいシーンだった。また、対照的に全体の分量としては少ないが、最後の方、フィリピンにおける演奏会のシーン。何の説明もなかったが、若い観客が扮装していたりして、ゲーム音楽の実に不思議な演奏会。
全体にケイト・ブランシェットの映画であり、彼女のこの役に対する没入感は凄かった。
2. 一番興味を引かれたテーマとその理由
「アーティストとは何か」、というテーマを私は感じた。天才で唯一無二であり、孤高で独りよがりであるがために、他者に嫌われて足をすくわれる場合もあるということ。
3. ラストシーンをどう感じたか
すべてを失ったフィリピンでの演奏会のシーン。ここでのTARは浮いているようだが、一方解放されたようにも見えた。指揮者として自分一人が音楽を重く背負うのではなく、肩の力が抜けて、みんなで音楽を純粋に楽しんでいるように見えた。
4. おすすめの映画音楽は
一番印象に残っているのは天才モーツァルトと凡人サリエリの確執を描いた「アマデウス」。
キューバの老ミュージシャン達のドキュメンタリー映画、ヴィム・ヴェンダース監督の「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」も大好き。
1. 最も印象的だったシーンとその理由
映画のはじめのころは少し退屈で、中盤に行くにしたがって面白くなっていった。それにしても難解な映画だ。
最も印象的だったのはベルリン・フィルで指揮者の座を追い出され、現指揮者の男性に暴力を振るおうとするところ。彼女の激昂ぶりが凄まじいシーンだった。また、対照的に全体の分量としては少ないが、最後の方、フィリピンにおける演奏会のシーン。何の説明もなかったが、若い観客が扮装していたりして、ゲーム音楽の実に不思議な演奏会。
全体にケイト・ブランシェットの映画であり、彼女のこの役に対する没入感は凄かった。
2. 一番興味を引かれたテーマとその理由
「アーティストとは何か」、というテーマを私は感じた。天才で唯一無二であり、孤高で独りよがりであるがために、他者に嫌われて足をすくわれる場合もあるということ。
3. ラストシーンをどう感じたか
すべてを失ったフィリピンでの演奏会のシーン。ここでのTARは浮いているようだが、一方解放されたようにも見えた。指揮者として自分一人が音楽を重く背負うのではなく、肩の力が抜けて、みんなで音楽を純粋に楽しんでいるように見えた。
4. おすすめの映画音楽は
一番印象に残っているのは天才モーツァルトと凡人サリエリの確執を描いた「アマデウス」。
キューバの老ミュージシャン達のドキュメンタリー映画、ヴィム・ヴェンダース監督の「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」も大好き。
上
上終結城さん (8g07wmfj)2024/11/7 15:39削除1.はじめに(ケイト・ブランシェットについて)
ケイト・ブランシェットの出演作は何本か観たが、印象に残っているのは『ベンジャミン・バトン数奇な人生』(2008)、『ブルージャスミン』(2013)など。とくにウディ・アレンのコメディ『ブルージャスミン』では、『欲望という名の電車』のブランチ(ヴィヴィアン・リー)と同じ「痛い女」を演じていた。(『エリザベス』(1998)は未見)
美人で硬質な大人の女のイメージがある。本作『TAR/ター』を観て、気位が高く近寄りがたい主人公と、転落し正気をうしなった主人公の落差を同時に演じられる女優だと、あらためて認識した。
2.課題について
【課題1】もっとも印象的だったシーンとその理由は?
【回答1】
リディアが夜中にメトロノームの幻聴に悩まされたり、ランニング中に悲鳴を聞いたように感じたりする場面。権威、権力を握った人間が否応なく抱え込む孤独や疑心暗鬼の象徴だろう。
【課題2】芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
【回答2】
<一番興味を引かれたテーマ>成功者の栄光と転落の落差。
<理由>
成功したカリスマ女性指揮者として音楽界に君臨するリディア。映画の前半は彼女の得意の絶頂が描かれる。同業者(指揮者)からアドバイスを求められれば上から目線でコメントし、音楽家の代表としての公開インタビューでは高邁な芸術論を語り、若い学生たちへは自分の音楽論を強い口調で指導する。楽団の人事権を握っているため、楽団メンバーや秘書たちからも怖れられている。
しかしその反動から嫉妬され、恨まれ、悪意をもたれ、多くの敵をつくる結果となる。誹謗中傷が起こり、やがてその地位から滑り落ちてゆく。その転落の落差が凄まじい。パートナーの女性にも去られ、落ち込んだリディアは、アパートの立ち退きを宣告され、ついに正気を失う。アコーディオンをでたらめに演奏しながら歌ったり、後任の指揮者を公けの場で押し倒して自分が指揮をとろうとしたりする。この場面のインパクトは強い。
【課題3】ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
【回答3】
地位と名声を失ったリディアは、若い頃に暮らした自宅(?)に帰り、自分の部屋にあったビデオを見直す。そこには尊敬する指揮者のメッセージが録画されており、自分が指揮者を志した頃の初心を思い出させるものだった。「音楽とは言葉にできない感情を呼び起こすことができる素晴らしいもの」リディアはうなずき、涙を流す。(このとき家に入ってきた男性(トニー)は誰なのか? 私は実の兄さんかなと想像した)
この後にフィリピンへ渡り音楽の仕事を再開したリディア。ストーリー的には、自分が音楽を志したときの原点、音楽の素晴らしさを再認識したリディアの新たな出発、と肯定的に考えることもできる。また皮肉に解釈すれば、かつてスポットライトを浴びたスターが地方巡業で細々と生きている哀れな姿ともいえる。私は前者のように解釈した。
すこしうがった見方をすれば、最後の場面はコスプレ集団のイベントであり、「祝祭」的な、カーニバル(しばしば仮装がおこなわれる)的な場である。音楽のルーツを考えると、人間の祝祭(お祭り)が起源かもしれない。そんなことも連想させた。
【課題4】お薦めの音楽映画があれば
【回答4】
思いつくままに列挙します。
『シェルブールの雨傘』(1964)、『エルビス・オン・ステージ(ドキュメンタリー)』(1970)、『キャバレー』(1972)、『ラ・ラ・ランド』(2016)など。
3.その他
本作の映像でおやっと思ったのは、シンメトリーの構図がよく登場すること。車がトンネルを走るシーンや地下道、高速道路、オーケストラの俯瞰など。この構図はスタンリー・キューブリックが好むことで知られている。そういえばリディアが乗る飛行機の機内は、『2001年宇宙の旅』に出てくる宇宙旅客機の機内に似ている。
ケイト・ブランシェットの出演作は何本か観たが、印象に残っているのは『ベンジャミン・バトン数奇な人生』(2008)、『ブルージャスミン』(2013)など。とくにウディ・アレンのコメディ『ブルージャスミン』では、『欲望という名の電車』のブランチ(ヴィヴィアン・リー)と同じ「痛い女」を演じていた。(『エリザベス』(1998)は未見)
美人で硬質な大人の女のイメージがある。本作『TAR/ター』を観て、気位が高く近寄りがたい主人公と、転落し正気をうしなった主人公の落差を同時に演じられる女優だと、あらためて認識した。
2.課題について
【課題1】もっとも印象的だったシーンとその理由は?
【回答1】
リディアが夜中にメトロノームの幻聴に悩まされたり、ランニング中に悲鳴を聞いたように感じたりする場面。権威、権力を握った人間が否応なく抱え込む孤独や疑心暗鬼の象徴だろう。
【課題2】芸術論、組織運営の重圧、セクハラ・パワハラ、陰謀と裏切り、ジェンダー…。一番興味を引かれたテーマとその理由は?
【回答2】
<一番興味を引かれたテーマ>成功者の栄光と転落の落差。
<理由>
成功したカリスマ女性指揮者として音楽界に君臨するリディア。映画の前半は彼女の得意の絶頂が描かれる。同業者(指揮者)からアドバイスを求められれば上から目線でコメントし、音楽家の代表としての公開インタビューでは高邁な芸術論を語り、若い学生たちへは自分の音楽論を強い口調で指導する。楽団の人事権を握っているため、楽団メンバーや秘書たちからも怖れられている。
しかしその反動から嫉妬され、恨まれ、悪意をもたれ、多くの敵をつくる結果となる。誹謗中傷が起こり、やがてその地位から滑り落ちてゆく。その転落の落差が凄まじい。パートナーの女性にも去られ、落ち込んだリディアは、アパートの立ち退きを宣告され、ついに正気を失う。アコーディオンをでたらめに演奏しながら歌ったり、後任の指揮者を公けの場で押し倒して自分が指揮をとろうとしたりする。この場面のインパクトは強い。
【課題3】ラストシーンをどう感じたか(どのように解釈したか)
【回答3】
地位と名声を失ったリディアは、若い頃に暮らした自宅(?)に帰り、自分の部屋にあったビデオを見直す。そこには尊敬する指揮者のメッセージが録画されており、自分が指揮者を志した頃の初心を思い出させるものだった。「音楽とは言葉にできない感情を呼び起こすことができる素晴らしいもの」リディアはうなずき、涙を流す。(このとき家に入ってきた男性(トニー)は誰なのか? 私は実の兄さんかなと想像した)
この後にフィリピンへ渡り音楽の仕事を再開したリディア。ストーリー的には、自分が音楽を志したときの原点、音楽の素晴らしさを再認識したリディアの新たな出発、と肯定的に考えることもできる。また皮肉に解釈すれば、かつてスポットライトを浴びたスターが地方巡業で細々と生きている哀れな姿ともいえる。私は前者のように解釈した。
すこしうがった見方をすれば、最後の場面はコスプレ集団のイベントであり、「祝祭」的な、カーニバル(しばしば仮装がおこなわれる)的な場である。音楽のルーツを考えると、人間の祝祭(お祭り)が起源かもしれない。そんなことも連想させた。
【課題4】お薦めの音楽映画があれば
【回答4】
思いつくままに列挙します。
『シェルブールの雨傘』(1964)、『エルビス・オン・ステージ(ドキュメンタリー)』(1970)、『キャバレー』(1972)、『ラ・ラ・ランド』(2016)など。
3.その他
本作の映像でおやっと思ったのは、シンメトリーの構図がよく登場すること。車がトンネルを走るシーンや地下道、高速道路、オーケストラの俯瞰など。この構図はスタンリー・キューブリックが好むことで知られている。そういえばリディアが乗る飛行機の機内は、『2001年宇宙の旅』に出てくる宇宙旅客機の機内に似ている。
池
池内健さん (9bsh1ffc)2024/11/10 14:27削除この感想を書くために見直してみて、音楽論をとうとうと語る冒頭の講演シーンは、オペラの序曲のようにストーリーの骨組みを予告するパートだと思った。
映画ではマーラーの交響曲第5番のライブ録音をめぐる動きがストーリーの軸になっているが、主人公は講演で「指揮者は時を支配している」「断固とした態度でオーケストラを率いなければならない」「5番はマーラーの妻アルマに捧げられている。だから5番を解釈するにはその複雑な結婚を理解する必要がある」「マーラーは病に倒れ、妻に裏切られたつらい晩年を送った」「しかしこの曲は悲劇のなかで生まれたのではなく若い愛の中で生まれた」「だから私も愛を選ぶ」と語る。そして主人公自身、指揮者として頂点を極めながら一般的でない形の結婚生活を送る。やがて没落に向かい、パートナーに去られながら「音楽への愛」とともに生きることを選んでいく。
このパートを削れば上映時間をもっと短くできただろうが、その分、奥行きを欠くことになったと思う。
【課題1】印象的だったシーン
マーラーの交響曲第5番を指揮する男をすごい形相で殴り倒すシーン。これで主人公は決定的に社会から抹殺されるわけだが、社会的地位よりも自らの芸術を守りたい芸術家としての強烈なメッセージだと思った。
オルガを誘ってレストランで食事を注文するシーンは、奔放なオルガに惹かれていく様子を繊細に描いていた。暴漢に襲われ顔にケガを負いながらオケのリハーサルに臨む姿も迫力があった。
【課題2】興味を引かれたテーマ
開高健は「コックが男で腕が立つならスケベに決まっている」と言った。料理人は味や店の雰囲気で客の官能を満足させることを目指しているから、日々の暮らしも官能に素直な生き方を選ぶということ。これは芸術家にも当てはまると思う。「官能から目を背けた芸術家」という言葉は形容矛盾だろう。
しかし、指揮者とか映画監督とか、チームを率いる芸術家は自らの欲望だけに従っていては作品をつくれない。集団をまとめる「政治」のために自らの欲望を押さえ込まなければならないこともしばしばある。しかし指揮者として絶頂を極めたターは政治よりも官能を優先させ(あるいは優先させているように思われ)、オケから追放されることになる。
一方、芸術の世界で官能と政治が絡み合ってきたことも事実だ。ターが師事したという設定になっているレナード・バーンスタインは同性愛者で、若い(男性)指揮者の間では「レニーと一緒にシャワーを浴びたら出世できる」と言われていたとか。ジャニーズ事務所の性被害も構造は同じだろう。この映画の中では、主人公のメンターのアンドリスが、長年メトロポリタン歌劇場を率いたジェームズ・レヴァインが少年に対する性加害で追放されたことに言及し、「セクハラ疑惑はごめんだ」「いまは疑惑があっただけで有罪だ」と嘆く。
ターはスキャンダルをきっかけにすべてを失うが、バーンスタインの「音楽には動きがあり常にどこかに流れながら変化していることを忘れてはいけない」という言葉に導かれ、芸術家として新たな道を切り開くべく東南アジアに向かう。その力強いまなざしは、政治的な正しさ(ポリティカルコレクトネス)重視の風潮に対する挑戦のようにもみえる。この作品が映画賞レースでふるわなかったのは、バーンスタインをネガティブに扱わなかったり、ジュリアード音楽院でポリコレにこだわる学生を論破したりしたことでポリコレ重視に異議申し立てをしているように受け取られたからかもしれない。
【課題3】ラストシーン
最初はショックだった。ベルリンフィルという世界最高のオケに君臨した指揮者が場末のコスプレ音楽会に出演するのだから。フルトヴェングラーやカラヤンがそんなことをするとは絶対思わない(思いたくない)。しかし、次の瞬間に、これは、ミュージカルにも積極的だったバーンスタインにならった新たな挑戦だと思い直した。ター自身、副指揮者をくびにするとき「指揮者の家は指揮台だ(楽団の部屋ではない)。スーツケースを持って旅をするのが指揮者だ」と言っていた。その言葉どおり、地位や権力ではなく、音楽に仕える芸術家として生きていく覚悟がすがすがしいと感じた。
【課題4】お薦めの音楽映画
「アマデウス」はモーツァルトが実に軽薄に描かれていて驚いた。しかし、社会の規範に縛られない自由人だからこそ素直に音楽の喜びを表現できたのだと思い直した。現代でいえば、桑田佳祐みたいな人だったのではないか。
映画ではマーラーの交響曲第5番のライブ録音をめぐる動きがストーリーの軸になっているが、主人公は講演で「指揮者は時を支配している」「断固とした態度でオーケストラを率いなければならない」「5番はマーラーの妻アルマに捧げられている。だから5番を解釈するにはその複雑な結婚を理解する必要がある」「マーラーは病に倒れ、妻に裏切られたつらい晩年を送った」「しかしこの曲は悲劇のなかで生まれたのではなく若い愛の中で生まれた」「だから私も愛を選ぶ」と語る。そして主人公自身、指揮者として頂点を極めながら一般的でない形の結婚生活を送る。やがて没落に向かい、パートナーに去られながら「音楽への愛」とともに生きることを選んでいく。
このパートを削れば上映時間をもっと短くできただろうが、その分、奥行きを欠くことになったと思う。
【課題1】印象的だったシーン
マーラーの交響曲第5番を指揮する男をすごい形相で殴り倒すシーン。これで主人公は決定的に社会から抹殺されるわけだが、社会的地位よりも自らの芸術を守りたい芸術家としての強烈なメッセージだと思った。
オルガを誘ってレストランで食事を注文するシーンは、奔放なオルガに惹かれていく様子を繊細に描いていた。暴漢に襲われ顔にケガを負いながらオケのリハーサルに臨む姿も迫力があった。
【課題2】興味を引かれたテーマ
開高健は「コックが男で腕が立つならスケベに決まっている」と言った。料理人は味や店の雰囲気で客の官能を満足させることを目指しているから、日々の暮らしも官能に素直な生き方を選ぶということ。これは芸術家にも当てはまると思う。「官能から目を背けた芸術家」という言葉は形容矛盾だろう。
しかし、指揮者とか映画監督とか、チームを率いる芸術家は自らの欲望だけに従っていては作品をつくれない。集団をまとめる「政治」のために自らの欲望を押さえ込まなければならないこともしばしばある。しかし指揮者として絶頂を極めたターは政治よりも官能を優先させ(あるいは優先させているように思われ)、オケから追放されることになる。
一方、芸術の世界で官能と政治が絡み合ってきたことも事実だ。ターが師事したという設定になっているレナード・バーンスタインは同性愛者で、若い(男性)指揮者の間では「レニーと一緒にシャワーを浴びたら出世できる」と言われていたとか。ジャニーズ事務所の性被害も構造は同じだろう。この映画の中では、主人公のメンターのアンドリスが、長年メトロポリタン歌劇場を率いたジェームズ・レヴァインが少年に対する性加害で追放されたことに言及し、「セクハラ疑惑はごめんだ」「いまは疑惑があっただけで有罪だ」と嘆く。
ターはスキャンダルをきっかけにすべてを失うが、バーンスタインの「音楽には動きがあり常にどこかに流れながら変化していることを忘れてはいけない」という言葉に導かれ、芸術家として新たな道を切り開くべく東南アジアに向かう。その力強いまなざしは、政治的な正しさ(ポリティカルコレクトネス)重視の風潮に対する挑戦のようにもみえる。この作品が映画賞レースでふるわなかったのは、バーンスタインをネガティブに扱わなかったり、ジュリアード音楽院でポリコレにこだわる学生を論破したりしたことでポリコレ重視に異議申し立てをしているように受け取られたからかもしれない。
【課題3】ラストシーン
最初はショックだった。ベルリンフィルという世界最高のオケに君臨した指揮者が場末のコスプレ音楽会に出演するのだから。フルトヴェングラーやカラヤンがそんなことをするとは絶対思わない(思いたくない)。しかし、次の瞬間に、これは、ミュージカルにも積極的だったバーンスタインにならった新たな挑戦だと思い直した。ター自身、副指揮者をくびにするとき「指揮者の家は指揮台だ(楽団の部屋ではない)。スーツケースを持って旅をするのが指揮者だ」と言っていた。その言葉どおり、地位や権力ではなく、音楽に仕える芸術家として生きていく覚悟がすがすがしいと感じた。
【課題4】お薦めの音楽映画
「アマデウス」はモーツァルトが実に軽薄に描かれていて驚いた。しかし、社会の規範に縛られない自由人だからこそ素直に音楽の喜びを表現できたのだと思い直した。現代でいえば、桑田佳祐みたいな人だったのではないか。
返信
返信7
Copyright © 文横映画好きの集い掲示板, All Rights Reserved.
Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)